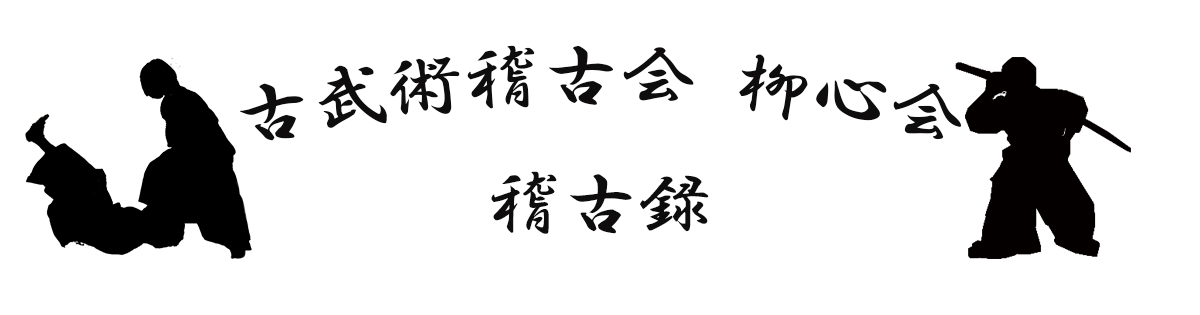古武術稽古会柳心会2025年03月15日稽古録
稽古日から寒の戻り、来週半ばまで寒くなるとのこと。桜の開花予報も来週には出る模様、春は、もすぐそばまで来ていることを感じる。稽古も柔らの流れが纏まってきたのでこの流れを切らさず続けたいところ。場の焦点もそろそろ合わせていきたいところ。

杖:道具を使って体側面・前後を緩やかに伸ばして意識を稽古モードへ持っていく。基本の構え・袈裟打をしっかりと練習する。直線・斜と相手を意識して遣るべき動きと守るべき事柄を一つのものとして動くことを目指す。
組杖:五本目
これまでの稽古で基本的な手順と型の概念は浸透しているのでそこから一歩進んで、それぞれの修正点を浮き彫りにしながら稽古を進める。打方の打ちを落すためには、逃げない気持ちを内外に表す必要がある。本心で遣るべきことを決め動いていく。そのために今の段階での動きを冷静に捉えて貰えればと思う。
剣杖:1本目
型の手順から次の段階として、要点を伝えていく。道具の強弱を知り活かすことが大切になる。その上で打太刀の身体に働きかけることを学んでいく。道具を扱っていても柔らと共通している部分を学んで行ければと思いながら稽古。
体術:金剛指の流れを遣いながら、前受身の練習。この練習の要点を掴めれば受けが上達していく。それは相手を捉え・見ることにも繋がるので感覚を磨いて貰えればと思うがどうだろう。
小手返:この日のやり方は、①抜きを掛ける②真下に崩す流れを作る③受け手に柔らかく後受身を取らせる。相手の状況を捉えて掛け合う。
遊び:螺旋掛け。思い付きで指先・手首・肘・肩へと螺旋を伝えて、引き崩す。この流れが体術・柔らでどの様な働きとしてでるのか、腕返しを参考に伝える。遊び稽古はあくまでも遊びなので、ここからそれぞれが動きの本質を掴み体術・型稽古に還元できなければ意味が無い。
手解:霞打もゆっくりと浸透中。
鬼拳:稽古後に気づいたが、基本的には利き腕側だけで十分。十分できる人だけが、逆を稽古すれば良いと思う。本能・反射を侮らないことが大切。基礎は指先をいかして、緩んだ状態で三角形を作り取り外す。今日の稽古では間取りはせず。
両手取:極めの形から少し応用もやってみる。古傳の動きには、人の持つ反射・意図を形にしている部分がある。稽古をしていると気が付く事柄が多い。肩を柔らかく落とすやり方は、基本なので身に着けて欲しい技術。
打引:鬼拳からの展開。打ち手の打ち方次第で、二通りのやり方がある。稽古中に会員からの質問で考察して説明。固定化する動きの場合は引かず・押さずその場で掛ける様にすることが大切。根本的にはその場にいる相手にその技を掛ける必要性はゼロなので意味はない。稽古の前提が違うので応用の一環になる。

剣術:上段からの打込みと受けについて丁寧に練習する。切先に重さを載せて体で打ち込む。受けは慌てず姿勢と道具のバランスを意識して、立体的な三角形を作る様にする。
切返:受けながらそれぞれのポイントを伝えながら稽古する。剣と体の一致・軸線と道具の合わせ・速さと早さの違いなど。各位それぞれの段階で上達はしているので、変わらず稽古を重ねて貰えればと思う。
型稽古:引疲
前回の稽古後に大きな間違いに気づいたので、その修正から前半部を段階的に稽古する。この型の寄太刀は非常に理不尽な姿勢を強いるのでやりづらく、道具のコントロールも難しくなりやすい。安易に動くと求める要点が簡単に崩れるので……。私も下手な稽古しか出来ないので積み上げて稽古していきたい。傾斜を維持し続けること、安易に向かないことが今日のポイント。