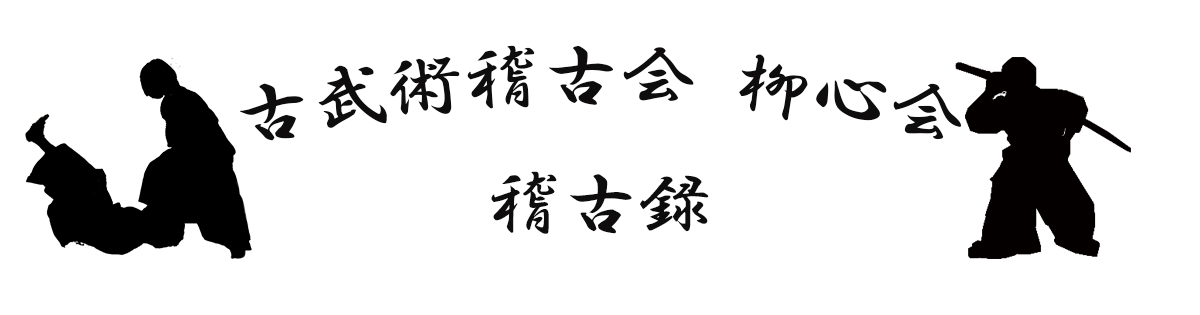古武術稽古会柳心会2025年03月22日稽古録
杖:袈裟打・一人杖と基礎稽古をこなしてから、巻落(単体・型)の稽古へ。
巻落:段階別に稽古内容を変えて稽古する。当会の基本的なやり方として必ず働きを作る・遣うというのがある。巻落なら【入る】という動きが大切になる。それゆえに廻る動きから螺旋の動きへと変化させていく。型稽古であれば、打方が突きを入れる動きに対しての対応として表現される。この時のポイントは、打方の働きを的確にとらえるということが大切になる。これを無視して動かないことが中位者以上の人は気に留めて貰いたい。
引落:剣杖型の導入として初稽古。基礎は上段構えから体の引く動きに合わせて真直ぐに打込む動きとなる。刀(剣)が鋭角・鈍角の働きをする時の対応技術となる。体で打込むことも大切になる。

体術・柔:受身は前廻受身を練習する。少しずつ頭部を入れる感覚が育ってきた感じをうける。丸く体を柔らかく使うために先ずは、頭部の入りがとても大切になる。縦に廻ることは先の目標。
霞当:手解きからの霞当も慣れてきた感じ。引かずに適切に手を外すことは柔らの基礎的な身法なので少しずつ理解が深まって貰えればと思う。
鬼拳:鬼拳に入る前に両手を抑えられた際の外し方を少し練習する。鬼拳は様子を見ながら間取も入れながら稽古を進めて負荷を強める。
両手取:崩す際に肩抜落を丁寧に掛けることを心掛けて貰いたい。肩を押し付けて下へ崩さないことが大切。初心者は肩抜→肩抜落の順番でも良い。
手鏡崩:十字受の形を作る際に手を外すことは、何気に大切なことだと稽古する中で気づく。心の持ち様が動きに出る。型稽古の中でも執着せずに柔らかく動ける心身になればと思う。手首からの螺旋的な働きと一教裏では崩し方が別の動きとなる。

剣術:基礎練習として刀(木刀)の落下から切に入る素振りを初心にもどり練習する。この働きを両手で行なうのが基本素振り①なので理解の一助になればと思う。
丁子素振り:膝の緩みを遣いながら練習。その後相対での受け・詰めを少し練習する。立てる動き丁子の形からだと自然に縦になるので感覚を掴むのにも良い稽古なのだなと改め思う。やり過ぎると腰を痛めがちになるので注意は必要。
格子:先の流れで段階的に稽古を進める。十字の働きは当会の剣術の中で姿を変えて潜んでいるので感覚を深める。
型稽古:引疲
先週に続いて引疲(寄り)を分解しながら手順からしっかりと練習する。左肘の課題はそれぞれ有るが、全体像を大切にしながら切先を意識した動きを表現していく。後半の受け流しからの体捌きで動きを先読みして、待太刀の動きを無視しない。自分勝手な動きをすると待太刀の動きが変わってしまい学びの機会を潰すことになります。稽古はお互いのものということを忘れずに。
居合:稽古中に逆手納刀のやり方について、質問があったので手順から練習する。納刀は稽古量が質向上に繋がるのでやり続けることが上達の秘訣となる。