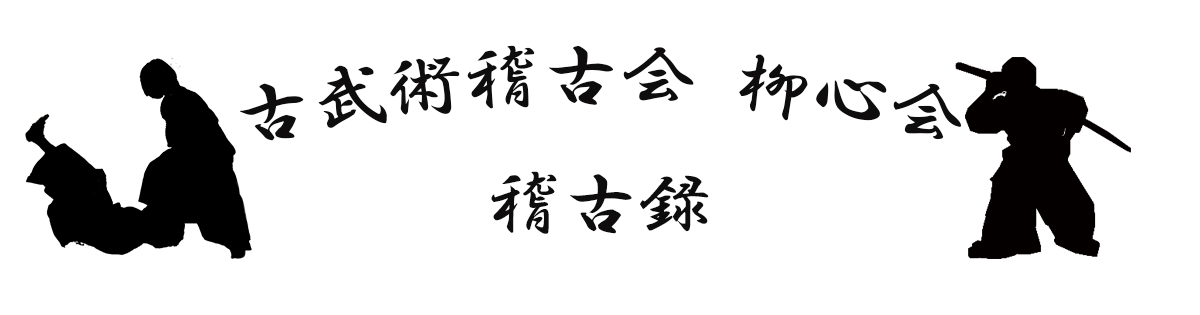2025年04月05日古武術稽古会柳心会稽古録
杖:杖を使っての膝の緩みを詳細に解説してみる。下肢を強く意識しなくても楽に動かすための単純なやり方。詳細もなにもないが自分の考えを整理する意味でも良かったと思う。
基本:袈裟打・受け(形)・引打(基礎)
それぞれの動きの要点を伝えていく。表層の動きをなぞって何にもならない。動きのポイントを体で理解するための一助となればと切に思う。教え・伝えることはできても自分のモノにするのは本人次第。
引打:先週に引き続き特訓の様な流れになる。各位の修正点が浮き彫りになっていく。悪い意味で適当な動きは、上達の妨げになることも見えてきたので今後の課題でもある。最後に袈裟打(木刀)を引打で落す練習する。
体術:金剛指・膝の緩み・足入替・前受身(膝附抜き)など。立った状態から足抜きをしてもらい前受身を見せようとしたが反応してしまいできず。後ろに意図(気配)を持って立っているだけで、身体が反応してしまう。特に足抜きをする際に平行に動かすのではなく、持ち上げようとされると身体が動かなくなる。古武道の師匠が云われたように抜く側の技術は難しく高い。
剣術:構え・素振りと基礎の稽古をしっかりと丁寧に進めていく。基礎の動きをおろそかにしているとやるべき場において見当違いなことをしてしまう。いつまでも初心者の振りはしないことが大切。
袈裟打ち・受け:打ち・受けともに何を確認するのかを話す。稽古を無駄にしないためのポイントなので、忘れずに今後の糧になればと思う。
中心立:刀(木刀)で受ける位置の基本は中ほどとなる。そのために先ずは切先を意識して扱う。手元で扱っていると場所が一定にならないので慌てずに受ける。
上級者稽古:この日の稽古では、各技術を上位者とそれ以外で遣るべきことを分けて行った。良くも悪くも稽古における各位の立ち振る舞いを見直すことになった。上を目指す・位置を知るのならやるべきことを毎回現す意識が大切になる。他者に頼っている限りそこにはいけない。
型:華車刀・三角切留・引疲
これらの型を整理した人の思慮深さを型の構造から改めて感じ入る。丁寧に稽古を積んでいけば必ず上達できる構造となっている。先ずは角をしっかりとつくり踏んでいき自分の中に矩を作っていく。馴染みの深さに合わせて角を取り滑らかにし消していく。
三角切留:待太刀の練習も少しずつ行っていく。寄太刀は各位大分馴染んできたので初級①はまずまず。廻刀での上段打ち込みをする際の体捌きが今後の課題になりそうなので各位しっかり意図して練習して貰いたい。
引疲:待太刀の受け流しからの打込みについて教導する。この部分はこれまで曖昧にしていたので反省するしかない。これがしっかり出来ていれば逃げるように捌く必要は無くなる。型稽古の良いところは遣るべき動きがきまっている(その功罪はさておき)ところ。それ故にそれぞれの段階で稽古ができる。その一端が各位に伝わり今後の稽古にいきてくれれば幸い。