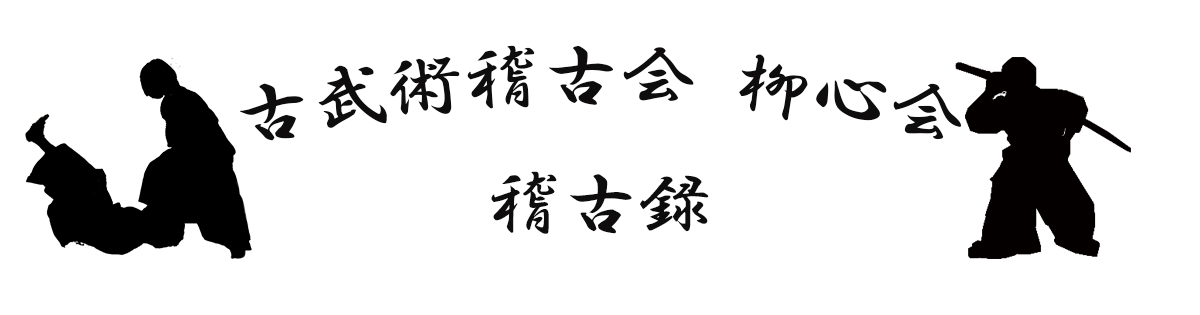古武術稽古会柳心会2025年04月12日稽古録

杖:膝の緩みから廻杖へ。久しぶりにするせいか杖の廻しで違和感が少し出てくる。動きに強張りがあり、流れも良くない感じで体に当てしまい落してしまった。少し反省!!自分に対しても侮ることが無いように気を付けていきたい。
袈裟打:最近入会したAさん。功夫の実践者で身体の遣い方だとかなりのもの、こちらの杖の遣い方に苦戦しながらも真摯に丁寧に稽古してくれる姿には有難い。打ち方は付ける感じが出てくると良い感じになるかと思う。
上打ち・切先返:切先返しから稽古を始めて、上下の打ちに繋げていく。杖の動く位置を軸線上から外さずに動けるようにしていく。先ずは手順と形から身につけていく。次はより身体の中を遣う意識で胸を緩めていく。
型:組杖1・2本目
一本目:突き躱しから打方の杖を打ち据えて崩しを掛けていく。この動きにフォーカスして練習してもらう。気をつけて貰いたいのは、ただ打たないこと。打方の中心を捉え崩すように働きを大切にする。
二本目:打方の袈裟打を受けてからの返し打ちを重点的にみていく。交点を活かしながら、打方の中心をおさえて袈裟打をするがその際に杖の両端を適切に遣える様に各位工夫が必要になる。打つ際に間合いを詰めすぎていて、打ちを不完全な形でしている人が目につく。彼我の間合いを絶えず把握する工夫と軸線の位置をみる。

体術:体術・柔で膝の緩みの稽古がどの様に表れているのかを解説する。基本的にすべての動きに緩みは遣われていると思って貰いたい。基礎稽古では横への軸移動の崩れを使って膝・股関節・足首の緩み(崩れ)を誘発させて、移動(順・逆)で足遣いを練習する。この日は、前面への崩れでより理解を深めて貰った。これはそのまま縮地(歩法・走法)の起点となる動きでもある。次の段階で手解肩返を使って実際にどのように足を遣うのかをみせ、体験してもらう。この理解がそのまま柔術での受けとなるのでこの基本的な概念と身法を身に着けることは非常に重要になる。これが身に付く(知る)ところから柔術の稽古が始まるともいえます。(私が師匠のところにいた頃は、その辺りの理解は部分的であり真似事の段階だったと今更ながらに……)出来ずとも理解が進んで柔術の稽古になる様になればと思う。
一致突:手足の一致を練習する。打撃的な力は求めていないので、一致することに専念して練習するのみ。
腕返:一致突きを捌いて、側面に入り腕返で崩しを掛ける。稽古の流れで口伝的なポイントを伝える。抜きと詰め基本的には同じなので、迷わない様に気を付けて貰いたい。

剣術:廻剣から三角切留・引疲の稽古へ。ここ数回集中的に稽古しているのでこれらの型に対しての理解と気づきが深くなっている。半身の入替・肘と膝の緩み・身体各部位の分離と制御などなかなか面白く楽しい感じになってきている。特に肘の緩みは非常に大切な要素なのでこの型稽古を通して理解を深めて貰えればと思う。
三角切留:寄太刀の寄せから稽古を始める。刀(木刀)の構えの変化と歩法の一致と斬りの姿勢を丁寧に練習する。特に待太刀への斬りを留めないことに留意しておこなう。中心へ斬り続ける働きを忘れない、自分の技量不足を誤魔化さないことが非常に大切になる。待太刀は後継→刀の寄せと寄太刀への斬りを軸線上へ縦に入れていくようにしていく。
引疲:待太刀は三角切留(寄太刀)の変化となるので、平正眼での付と身体の三分割・肘の緩みがポイントになる。先ずは、一動作ずつ分割して丁寧に動く様に心掛けていく。待太刀は寄太刀との間合いと付けられる感覚を得ていく。そこから誘いに対して、初伝遣いでは、寄太刀の頭部へ縦に明確に斬っていき受け流され崩されたところから姿勢を低く保ちながら刀(木刀)を返し切り上げる。寄太刀は誘い、受け流し待太刀の頭部が観えたら上段打でしっかりと切込む様にする。この際適切に受け流しが出来ていれば、待太刀の切先返を躱しているので慌てないことが大切。結果的に双方の上下打ちが交わり型納まる形となる(初伝遣い)