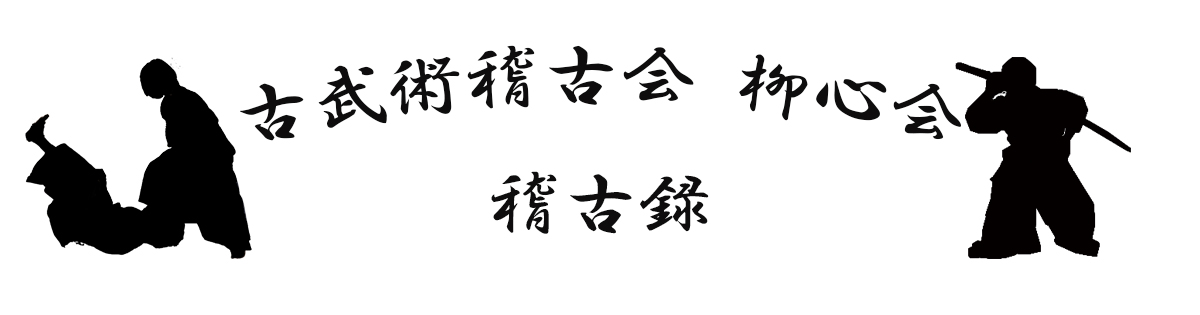古武術稽古会柳心会2025年4月19日稽古録
杖:稽古場に向かいながら、縦機転を中心に練習しようと決めていく。重要な動きだが稽古していなかったことを思い出し反省も込めてしっかりと練習する。身体を割って遣う要素もあるので身体訓練の一環でも有ったりする。
足の緩み・一人杖で身体を温めて、縦回転の基礎練習へ。稽古場のわかり易い線を活用して、なるべく体の軸線がその線から外れない様に杖を遣いながら練習を進める。

縦回転:端的に言い表すと半身の入れ替えとなる。身体の入替をなるべく小さくすることで横揺れを最小にするとも云える。杖や薙刀を稽古することで、刀や素手で学ぶよりも最短で概念・動きを体感・習得できると思っているので会員には頑張って貰いたい。
三方突:切先返の付と縦回転にフォーカスして練習していく。それぞれの練度に合わせて、対人で進めていくが全員距離が少し遠かったのは残念!!(一足離れてから始めたことで勘違いさせたかも……。)
型:三本目(打方:木刀)
打方は木刀でこの日は稽古する。誘いの間合いと刀(木刀)の捌きを重点的にみる。誘いをする時は止まらないことがとても大切。動きながら誘うことで、相手の間合いを盗むことにも繋がり、拍子の間も見えてくるようになる。
最後の数回は打ち込みの強度を高めて稽古を進める。この様な稽古する時に自分の動きを決めつけて型に入ると私からダメ出しを貰うことになるので、会員各位は気を付けて貰えると有難い。自ずと間の稽古となるので、構え・付・捉えなどに甘えが出るとやり直しになる。

体術:先週伝えた崩れと柔らの緩みについて軽く触れて稽古を進めていく。半身構えから縦の意識で入替を練習。その表現で入身崩しへ入る。
入身崩し(向):半身構えから手首の交点をいかして正面に入身し崩す練習。ポイントは、真直ぐに進み入る。特に足から入ることが非常に重要になる。視界に入る受けの腕に執着して外すことを主とすると入れないので気を付けて貰いたい。この動きは他の体術・柔らでも同じなので個別の動きと考えないこと。
鬼拳・両手取:柔らの基本となる稽古なので動きの基本を学ぶつもりで、集中して取り組んで欲しいがどうだろうか?掛けることに拘らずに一動作毎に丁寧に動き呼吸も合わせる。
下藤:頭部に対して崩しを掛けるので、抑える・引っ張るなどの動きは厳禁。受けの軸を読み取り、それに回転を掛けることで崩し裏を取る。特に頭部への働きは意図せずに事故に繋がる可能性が有る。取・受丁寧に動くことを心掛ける。誠実さを持って稽古することが上達の秘訣でもある。
剣術:腰構えをしっかりと作ってから、素振りへ。素振りで学ぶ基礎となる動きは型稽古の中で形を変えて使われるので技術向上を意識して練習して貰いたい。
打ち受け:頭部への打ちとその受けの基本練習。始めは体を入れる感じは出さずにそれぞれの段階に分けて。受けがある程度できる人は様子をみて体をいれて重さのある打ち込みの受ける練習もおこなう。
中心立:受けからの中心立は足の動きと一致させることを念頭に精度を高めていく。単独の技術稽古するとそれ単独と捉えて学ぶ人が多い様子。

型稽古:華車刀・三角切留・引疲(寄・待)
華車刀:袈裟打ちの三連打に付いては、基本が出来る形になったら拍子を工夫することが必要になります。途切れずに連綿とした雰囲気を意識して出来る様に工夫する。待太刀は、寄太刀の動き(拍子)を捉えながら、適切な受けをする。
三角切留:寄太刀は肩先への打ち込みに付いて技術と理解を深める様にする。受け流しの形は軸をしっかりと立て一重身(真半身)に近い半身を作れる様にする。寄太刀は先ず軸線上にしっかりと切込んでいく。その上で受ける形をしっかりと作る。双方上達してくると自ずと重み速さが出てくるので緊張感を持つ癖をつくる。
引疲:段階的な技術の習得が非常に重要だと改めて感じる稽古であった。同時にその動きがどの様に型の中でいきてくるのかをしっかりと見せて理解できるように道筋を作る必要性も感じた。
寄太刀の流れは、①刀を上段に対して付ける②誘いを掛けて打込ませる③ラインを外し受け流す④頭部へ打込む(切先返しをおさえる)待太刀の流れ、①上段で待つ(歩みの雰囲気を持って)②付けられ静止する③誘われ寄太刀の頭部へ打込む④受け流されて、打ち廃る間で縦に切先返す。(寄太刀が結果的に刀(木刀)をおさえる)