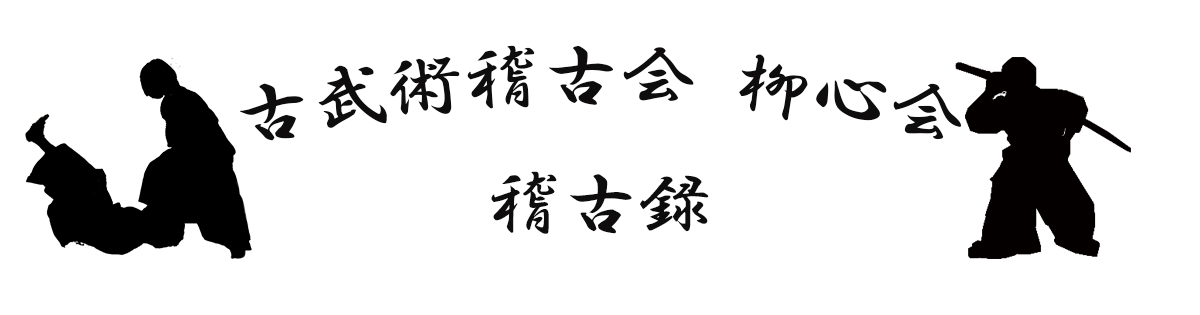古武術稽古会柳心会2025年05月03日稽古録
気が付けば五月最初の稽古日。ここ数ヶ月剣術型の三角切留と引疲を集中して稽古しているお陰か型の理解が大分進んできている。昔兄弟子から師から離れて数年してから様々な事柄に気付かされると云われたが、まさにその通りになっている。有難いことだと噛みしめて、自分なりにゆるゆると歩みを止めずに来て良かったと思いながら稽古場へ。

杖:膝の緩みから構え・袈裟打ちへ。袈裟打ちで杖先がどの様な軌道を作るのかを段階的に解説する。杖も最短で動くことを考えると付ける表現に移行していく。払い打ちから付ける打ちへの変化は上達への道標になる。
型:組杖1~6本目
上級組はそれぞれ打方・仕方を交互に交代しながら型を進めて貰う。その時々のポイントを伝えて工夫して貰う。特に六本目の打ち返しに対して仕方の体を捌いていく動きは、基本組太刀二本目の動き(高伝)なので良く練習して貰いたい。
初級組は型の手順から教習を進める。一本目の突き躱しは打方の杖を払わないこと・杖の崩しをとおして打方の肩を抜くことが大切なポイントになる。一本目で学ぶ理は基礎となるので少しずつ理解と習得を進めて貰いたい。
三本目の打方に対しての誘いと間合いの詰めについては、打方の反応しだいで仕方の対応が変化するので、相手をよく見て捉えて動くことが求めらる。

柔:足の入替中に受身(前・後)をいれて練習してみる。後受身は転がる形になってしまったが素の反応だったのでこんな感じかと納得する。後受身の形へ誘導するには、まだ意図が必要になることが判ったので、練習の指標がみえた感じになった。
呼吸法(立ち):立ちで相手への詰めと崩しの基礎を練習する。肩抜の様々な形を稽古しているが、それがどの様に活かされているかの視点が浅い様にみえる。今後の課題でもあるので少しずつ型稽古・部分稽古で理解を深めていけるようにしていきたい。
動きを見ると抜きよりも詰めた部分の維持と誘導が課題の様子。左右の差(バランス)で崩す場合、詰めた部分は土台となることが多いので、抜くことで動かすのではなく詰めた部分を活かすようにする。
小手詰:受けの小手を取る時は、適切な間合いを先ず取り、その後抜きを掛ける。取りは手首に力を入れると受けに負荷を与えやすいので、丁寧に掛けることを心掛ける。
両手取:各位だんだんと形になり始めた感じ。肩抜時から真下への崩しは肩を押さずに、撫で落す雰囲気が出る様に工夫が必要になる。技において雰囲気はとても大切な要素なので、研究・工夫すると面白い。

居合:この日は立居合の希望があったので1〜4本目まで動きの手順から稽古を進める。立居合は歩みと抜き出し・斬りの形を覚えたら一致させていくことが大切になる。細かい動きに囚われずに一致を心掛けて稽古して貰えたらと思う。先ずは柄頭・鞘先・切先などの「先」の部分を意識して、各動作を丁寧に抜いていく。
右一文字:横払いの切先の位置を伝える。これは縦の斬りの際も同じことなので忘れずにしっかりと覚えて貰いたい。この日は前半の横払いを集中的に練習する。
左膝行突:鞘送り・抜き出し・撞き共に下肢の動きと一致させていくことがポイント。撞く前の抜き出した際の姿勢と切先の位置関係を理解して出来る様にしてください。
剣術:受け流し・上段での打ち込みを切らずに全員で練習する。上段の打ち込みの際に柄頭を下げずに打ち込めるように鍛錬が必要(低く打ちこむ際は、膝・股関節を緩めて低くしていく)
型:引疲・獅子乱
引疲:寄太刀は肩を開かない運剣・待太刀は誘いと切る位置・切先返をポイントに稽古を進める。Aさんの切先返は肘が緩んでいるので、動きが消えたかのように切先が返ってきてなかなか面白い。各位、寄太刀の運剣も各位徐々に慣れてきた感じ、これからはより細かいポイントに入れる雰囲気が出てきた。
獅子乱:寄太刀は先ずは受けること。この受ける位置・技術を磨いていく。待太刀は予備動作なく、適切な間合いで切込んでいく技術を高める。体捌きを身に着けるために段階を踏んでいるので、稽古時のポイントを忘れずに次の段階をイメージして稽古を重ねて貰えればと思う。