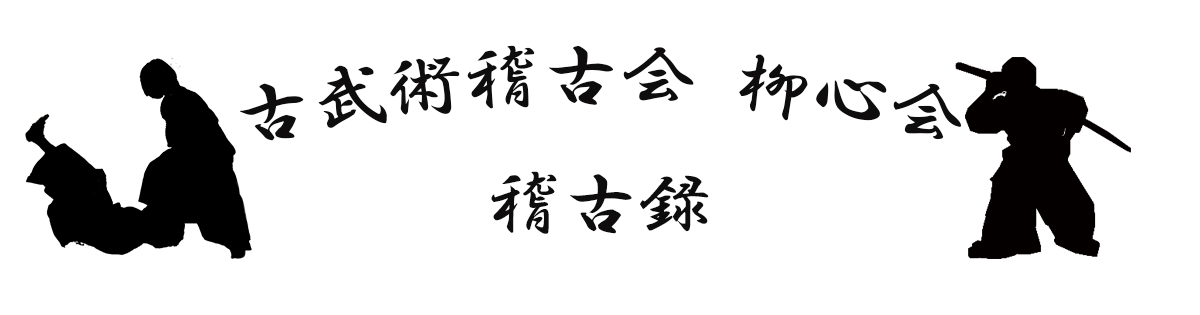古武術稽古会柳心会2025年05月10日稽古録
杖:膝の緩み・廻杖・袈裟打(単・相)・逆袈裟打・組杖5・6本目
柔:金剛指・肩・胸の緩み・膝の緩み・足入替・前受身(膝立ち抜き)・背落(構え→後取)・霞当・両手取・小手詰
居合:一文字抜・正面切・鍔返・立居合1-2本目・立居合5本目(前半)
剣術:構え・廻剣・捌き・引疲

杖:組杖の六本目(巻落)から型稽古を始める。打方の突きに対して合わせて(後の先)で杖扱い巻落を掛けていく。この時に交点を活かさずに、突き入れてしまうと払う動きになりやすいので気を付けて貰いたい。ある種の受身的な余裕を持って動いていく。巻落からの打方の返しに関しては、それぞれ慌てずに対応が出来る様になってきたので上達している。次の段階としては、打方との間合いと弾きの技術の向上かと思う。以前も書いたが、基本組太刀二本目で使う体捌きと同じになる。打方の位置と道具の方向を捉えて動く様にする。
五本目の杖捌きと体捌きの一致を今後は求めて行こうかと思う。体捌きの結果として、打方の右こめかみに杖の先が入ってくる。これは打方とすると見えないので、打方から見える位置で終わっている場合は間違っているので、指標になるかと思う。

柔:中国武術時代に教わった宋氏形意拳から龍形基本功を借りて、胸と背中の緩めをおこなう。この時に龍腰は使わずに股関節・膝等の下肢の緩みと軸を使っておこなう。宋氏形意拳は非常に柔らかい武術なので、思考が固くなりがちな人には苦労が伴うが得るものが大きいと今更ながらに思う。
前受身の工夫として、膝立ちからの足抜きでおこなう。足抜きの技術は良い稽古になるのでこれからも折を見て出来ればと思う。
両手取は立ちと坐りで行う。鬼拳から左に捌く身遣いが難所の様に見えるが、地道に少しずつできるように頑張っ貰いたい。膝行膝退をおこなっていないから、仕方が無いが時間もないから……。肩抜の部分も少しずつ慣れて来た感じがあり良い流れ。
小手詰:この型で先ず知って貰いたいのは、間合いの取り方。逆関節の決め方や崩しではなく、向き合う相手との適切な距離感を掴む。制すためにまず何が必要かを考えて動いていく。
居合:先週に引き続き、立居合を練習する。歩みと抜き・斬りの一致。そこから細かい技術の修正と理解へと進んで貰えればと思う。特に柄頭・鐺・切先などの先の使い方も立居合では捉えやすいのでその辺りにも意識を割いて貰えると先々いきてくるかと思う。
鍔返の延長で立居合五本目(後影身)の前半部分を稽古する。この部分は、身を振り返らず半身のまま切先を後ろに飛ばしていく。師匠から教わっていた頃に見返り美人の様にと云われた。後半の袈裟切・逆袈裟切に付いても少し解説する。姉弟子の居合を思い出す。

剣術:廻剣の流れから半身で受け流しの捌きを練習する。三角切留・引疲でこの受け流しの身遣いは非常に活きてくるので基礎稽古から理解して貰えればと思う。
引疲:寄太刀・待太刀の動きを説明してからグループに分かれて稽古を進める。刀の寄せ方と身遣いの一致。待太刀の打ち込み、切先返のやり方など。現在稽古しているものは初伝遣いなので型通りに動いて形をしっかり作る。基礎・基本を養成する段階。
寄太刀をする際に、待太刀に対して正しい位置に立つことを忘れずに。中心を捉える・取る≒立ち位置が正しい訳ではない。逆に自分にとって優位な位置から始める身勝手な振る舞いとなるので、無自覚でいない事。特に私に対してその様に立つと苦言の元になるので注意が必要。
受け流しの形を各位少しずつ取れるようになってきたので、そこから適切な滑らかに落ちる間と形の習得・体得が今後の目標になる。