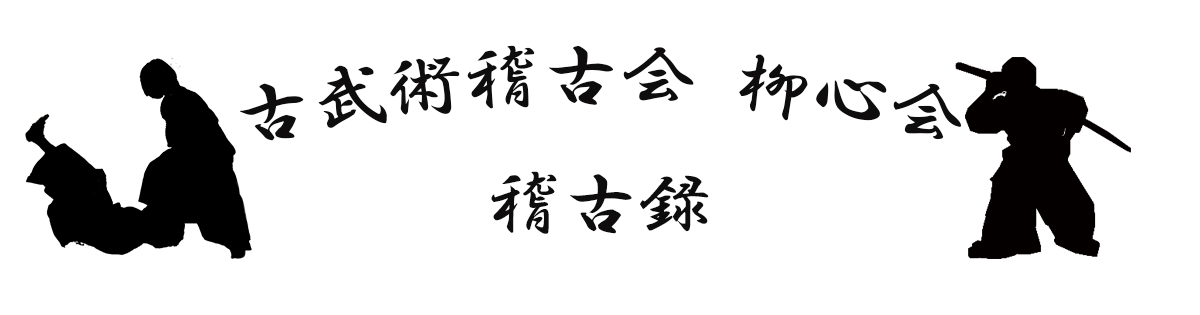古武術稽古会柳心会2025年07月19日稽古録
杖:腰の緩み・構え・袈裟打ち・松風・巴・一人杖・型:組杖1-3本目
体術:呼吸法・軸作り・膝の緩み・足入替・後受身・構え・坐技呼吸法・柾目返(基礎・①・②)型:両手取
居合:一文字抜・向・坐居合八本目・各自課題
剣術:構え・袈裟打ち(受け)・切返・基本組太刀四本目(部分稽古)
小太刀:構え・切落(相小太刀)・型:波立・受流・横雲
梅雨明けも出た翌日の天気は朝から快晴。汗をかきながら稽古場へ。稽古場の窓を開けて、場をゆっくりと掃除しながらこの日の稽古内容をアレコレと考える。

杖:稽古前に真面目な話をしていたので、少し固い感じになっていたので杖を使った腰の緩みから開始。杖の両端を意識しながら股関節を中心にほぐしていく。
松風:打ち払い時に杖の動きに身体が引っ張られやすいので、軸をしっかり維持して打てるようにしていく。打ち払いの動きは撞木の作りと一致できる様にもしていく。
巴:基礎と基本を段階的に練習していく。まずは真直ぐの打ち・体捌きを徹底して身に着けていく。その動きと意識をもって斜めの動きを重ねていけるように練習してもらいたい。打力を上げるための身体操作などは気にせずに体捌きと杖が一致することが、最優先となる。
組杖:打方へのポイントにフォーカスして練習を進めていく。仕方にはその解説をとおしてやるべき動きを理解してもらう。打方(打太刀・受け)が判らなければ仕方(仕太刀・取り)が本来やるべき動きを理解することは難しい。打方を学ぶ会員の成長は嬉しく思う。
一本目:中心の捉え方と追う動きの程度について少し話をする。捉えることを第一にし過ぎて型を壊しては本末転倒になる。成り立たせると動きの質(やるべき動き)を図り動くことが学びになる。
三本目:打方は杖をどの様に扱い打ち込むのか理解し動くこと。安易に動き、似せた動きで出来ていると勘違いしないこと。胸・肘の緩みで淀みなく、無理なく杖を扱い打込むことが基本となる。仕方は、切先返の動きと体捌きのバランスを適切にしていく。

体術:段階をおきながら呼吸法をしばし行う。足芯呼吸法も織り交ぜて心身を落ち着かせていく。呼吸法を真剣に練習するには時間が足りないのが残念ではあるが、日常の中で少しずつ理解と体感を深めて貰えると嬉しく思う。
後受身:軸上に沈みながら、背中・後頭部を丸めて転がる様に受身を取って貰う。受身の練習は反射との戦いとも言えるので、まずはポイントをしっかりと身体に同化させていく。
坐技呼吸法・柾目返:受け手は取りの手(腕)をどのように取っていくかが非常に大切になる。漫然と掴む・受けることは百害なので、その都度適切にできているか自問して、臨むことが難しくとも非常に大切になる。掛けては、胸・肘の緩みを意識しながら適切にやるべき動きをおこなう。
肘の緩み:押し上げる動きはぶつかる動きになりやすい。動かなくとも安易な部分に逃げずに立てる様に緩めて扱えるように工夫していく。万人に有効な最適解はないので、相手をとおして自分と向き合っていく。
居合:向で付・半身・切を丁寧に練習していく。向は型ではな、各動き・要素を丁寧に出来ているか確認していくためのモノ。その意図を良く理解して抜いて貰いたい。
坐居合八本目:型の手順を伝えていく。出来ずとも守るべき事柄と今やるべき事柄を捉えて練習していくことが大切です。①切先返のやり方と中取の形を両立させる②腹抜時に右手・腕の遣いを強くしない③下肢の捌きと刀の動きを一致させていく……。まずはこれらを成立させる。特に①の動きが最初のキーポイントになるので気を付けて抜く。

剣術:切返を見るとそれぞれの段階としては、悪くない雰囲気。次の段階に入るための準備と下手になる覚悟が持てるかが上達の決め手になるかと思う。置きにいかずに打つ・切る表現の違い。刀と体の一致と重さと速さの載せ方など。現状の正しい動きを否定してそれぞれ上達へ繋がる道に入って貰えればと思うが……。
基本組太刀四本目(部分稽古):手順・形から、型稽古として必要になる動きの解説と各ポイントを伝えていく。打太刀は刀捌きの習得と間合い・拍子の精度を上げていく。仕太刀は、切先の遣い方と入り身のやり方を学んでいく。足から動くのではなく、切先を活かして刀に動きを導いて貰うようにする。打太刀は自分の打ちを完全にコントロールする術を身に着ける。
小太刀:相小太刀で切落から始める。道具に沿って打込まない事、相手の中心を割り、押さえていく動きを行なっていく。
型:波立・受流・横雲
波立:①受ける②当てる③外すの三段階・三種類の動きがある。①の受ける形から学び、動きを深める。短いもので守る術をしっかりと出来るように学んで貰いたい。
横雲:波立の動きから打太刀の小手を押さえる形へ入り、体を捌いて脇を撞く。左手の遣い方は稽古時に伝えたのでその形が出来るようにしっかりと覚えてください。脇を刺す際の足捌きは、打太刀との間合いをコントロールすることになるので適切に取るようにする。