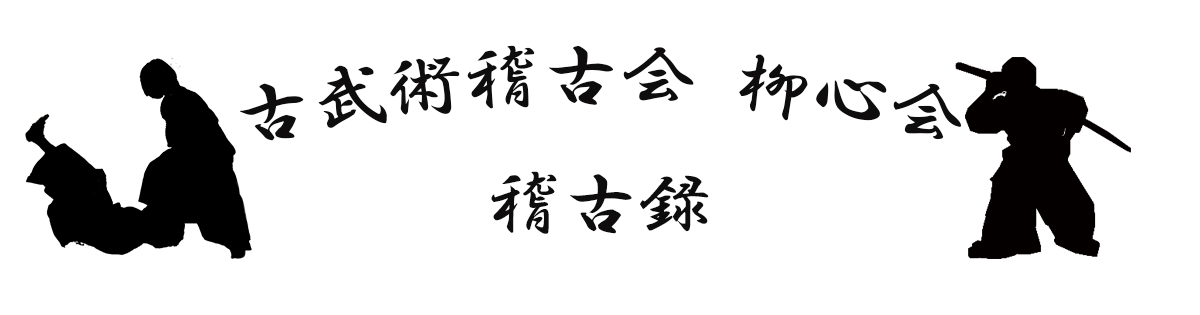古武術稽古会柳心会2025年07月26日稽古録
杖:膝の緩み・松風・巴・一人杖(新・旧)・型:組杖1-6本目(仕方)
体術:軸作り・膝の緩み・構え(入替)・中心捉え(前進・後退)・逆手返(後受身)・小手返・手解き・型:両手取・小手詰・肱押
剣術:小太刀(構え・素振り・切返・受流・肘取)型:波立・受流・下段詰
居合:一文字抜・腹抜・腹抜突・向・型:坐居合七本目・各自課題
毎年この時期から始める小太刀稽古も少しずつ形になって来た。来月中旬には二刀の稽古に移行していくから小太刀の感覚を一歩でも前に進められれば良いなと思う。道具の長短を感じ掴み変わらずに扱う。その感覚を少しでも会員に伝えられればと願う。

杖:稽古場も程よく冷えて稽古開始。杖の両端を意識して膝を気ままに動かしていく。構えから体の入替・素振りへ。
松風:道具の動きと体が一致するように動かしていく。特に払いと撞木が一致するように丁寧に行って貰いたい。
一人杖:旧式から振っていく。上下の打ち分けを丁寧に打っていく。速さよりも一致した動き・適切な打ち方を求めていく。技と技の繋がりも無理なく体捌きで繋げる事を大切にする。新式の練習に移行したら、一瞬手順が霧散してしまい焦ったが身体の動きにしたがってこなしたら戻ったので良かった。
型:組杖1-6本目
打方として遣るべきことが出来ているか、自問自答しながら身体を動かしていく。全般的に自分の甘さ(稽古不足)が出てしまった形だったので改善点が多い。仕方(会員)が上達し段階を上がり始めたのなら、自分もその先を具えて動いていかなければ先へはいけない。自分と向き合えた稽古であったことは実りであった。
四本目:打方の中心を捉え詰めて、崩しを掛ける時に仕方の軸が前のめりになってしまうと崩し切れずに終わってしまう。そのバランスを取れる様に焦らず、先を確定せずに動くことが大切。崩し極める時の立ち位置も各位今後の課題かと思う。

体術:構えから入替へ。構えを取る時は上の腕よりも下の手刀を正しくすることが非常に大切。これは腕を落した半身構えの時には後手となる。これを正しく取れるようになれば上位者と云える。
中心の捉え:互いに構えた状態で、手首の位置に交点をつくり前進後退を通して中心を捉え合う。この時に相手の構えが崩れずに動く間を掴む様に心掛けて貰えれば良いかと思う。
逆手返:先の稽古から受身の練習を兼ねて逆手取をおこなう。半身で入り、鎌手に取って真下に崩す(受けを取らせる)形にもっていく。この形は肩抜落の一形態とも云えるので、受けの中心・肩へ働きかける。
小手返:腕から螺旋に掛けて受け手に中心・下肢への崩しをかけていく。Zさん功夫の稽古で肱の力が抜け、遮断されていて良い学びになった。この日のやり方だけでは崩せない。掛ける事は大切だが、そこに固執すると受け手に勘違いさせてしまうので掛からない事実を受け入れる。※受け手は掛け手が思う以上に良く見て学んでいる。
型:両手取・小手詰・肘押
両手を取らせた形から始める。この時に受けは漫然と持たず、剣術を変わらない持ちが出来ているか問いかけながら練習して貰えると良いかと思う。握って握らずの感覚を掴んで貰いたい。※緩みがちになることも一時は大切な事。
小手詰:受け手の腕を一直線にして、手首→肘→肩→中心へ繋げていく。最後に下肢へ働きかける。手首・肘だけだと慣れた人や腕力がある人には掛からないので、安易な形にとらわれない様に気を付けて下さい。

剣術:小太刀を持って、構え・基本素振りを練習していく。より半身を意識して構えを作っていく。小太刀は半身の身遣いを学ぶのに最適なので、練習毎に形・動きを作って貰えればと思う。
肘取:横雲(型)への導入練習としておこなう。受けを作り半身で入身して、柄から崩しを掛ける。この時に柄を上げる事で受けがなぜ崩れるのかが掴めると柔も上達していく。剣術で学ぶことも柔と変わらない事の一例としても面白い。
小太刀:波立・受流・下段詰
受流:まずは受けた形から半身になり太刀を流す。この時の身遣いはやや真半身に近くなる。腕で太刀を退かさずに切らせる流れをいかし続ける感覚が大切になる。布一枚分の守りを身に着けることにも繋がるかと思う。
下段詰:正眼の構えを崩さずに寄っていくことが最初の関門。突かれる恐ろしさを受け入れて構え・誘うこと。(個人的に下段に構えられたら寄りたくはない)その上で突きの間を捉えて押さえて詰める形をつくれる様にする。
型:右転左旋
久しぶりに稽古する。まずは受けて流す形から練習していく。途中から本式の形でも練習する。Kさんはこちらの助言をしっかり理解して、良い動きを見せて驚かせてくる。嬉しくなる。受ける形・間が分かると様々な部分で応用・変化が出来るようになるのでこの初伝遣いをモノにして貰いたい。
居合:向の練習をとおして、坐居合一本目の身遣いを解説する。付ける事・半身・腕を立てる事など。単純な形から型へ還元できるようになれればと思う。
坐居合七本目:この日は、寄せと浮身・斬りと撞木足の一致を意識しながら練習していく。型として纏める時はこれらを一つとして抜いていく。想定を解説しながら斬りとの一致、腕の処理について話を。