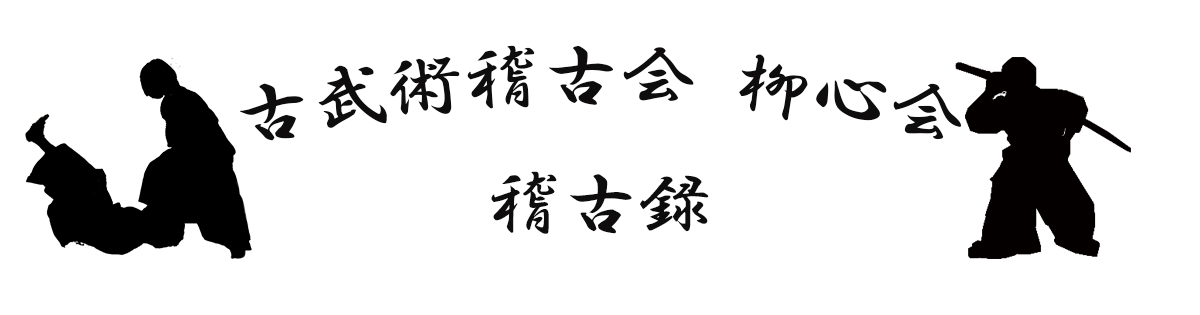古武術稽古会柳心会2025年08月02日稽古録
杖:膝の緩み・袈裟打・巴・松風・切先返・上打・一人杖(新旧)・組杖1-2本目
体術:軸立・膝の緩み・構え・軸崩・肩抜(受身)・鬼殺・両手取・小手詰
居合:一文字抜・縦抜・立居合1・5・6本目
剣術:構え・廻剣・切返・受流(基本・各種)・切落(基本・先後)
小太刀:構え・波立・受流・横雲・越拍子

杖:杖における膝の緩みを詳細に解説する。段階的にどの様に動くのか、意図はどの様にするのかなど話してみた。どの様な事であれ表(言葉にする)にしていくことは、前に進む糧になる。
基本打ち:袈裟打ちでは、杖を握らずに練習してみる。基本的に持ち方は剣術と同様し、その中でも杖はより自由度が高い握り(握らない)を重要している。常に手放すことを念頭に置きながら、動き工夫ができればと思う。
松風:撞木の開きと打ち込みが一致することに焦点を当てる。腕で扱う限り一致はしてこないので、視点を変えて工夫して貰いたい。
一人杖:袈裟打ち・膝打ちの打ち分けは入念な練習が必要。速さと正確な打ち分け・表現が一致できるようにすることが技術の向上に繋がる。
型:組杖一本目・二本目
一本目:突きの強度を上げて練習する。突かれる間を捉えて動くことが肝要になる。間合いが近づき動いてしまうと打方に追われ刺されてしまう。相互の間を重視して捌く。次の課題は杖を捌き(扱い方)となる。ポイントは肘の緩みと空間の作り方。練習で伝えた事を各自工夫して習得して貰えればと思う。
二本目:両腕を伸ばすこと。これが習得できないと間合い・間を自分のものにすることは出来ない。基本的な注意点がなぜ大切か考えることが必要となる。最後の縦回転からの突きは、打方次第で位置が変化する。

体術:軸作りから対人における軸崩しを練習する。これにより取・受けの学びが深まる。特に受けは施された形を表現するため、受け方入門としても良い練習となる。前傾の掛け方が後傾になる働きはなかなか興味深く学びになった。
型:両手取・小手詰(共に立ちで練習)
この日の練習では真に肘・肩が緩むと掛ける事が難しくなる事がよく理解できた。これを掛ける事に拘り工夫して自己満足に固執すると学ぶべきことがズレてくる。掛からない事も学びの大きな一つである。

居合:立居合を中心に稽古を進める。歩みと抜き・切の一致をどの様に表現していくかがそれぞれの工夫となる。縦抜は片手斬りの基礎を学ぶのに最適なので各自より楽に抜ける様にして貰いたい。
立一本目:段階的な練習では、刀を大きく寄せていくが型稽古ではその動きをより小さくして抜いていく。この辺りの理解と動きは連動しているので注目ポイントの一つとなる。
五本目・六本目:刀の抜き方と肘の緩みがより求められる。それぞれの型で抜いた時の切先の位置がどのあたりに有るのが正解か確認して貰えると上達に繋がるかと思う。袈裟切・逆袈裟切は方向・位置を考慮することで動きが整う。

剣術:大太刀で基本各種を練習してから小太刀へ。※稽古後に中心立を遣り忘れたのは反省点。波立の動きは良い感じだったので来週辺りから次の型へ進めるかと思う。今期で基本型を一通りできれば何よりだけどどうか。
受流:各位留めからの動きはそれぞれ良い感じ。基礎が少しずつ身についてきている。上位者はそろそろ形を崩す意識が必要かと思う。型稽古で必要になる動きも練習して貰えたらと思う。
切落:基礎は受けの軸線上を真直ぐに斬りにかかり捉えて収束させること。切りわる動きを掴めるように各位の工夫が必要か思う。道具の形状に惑わされないことも大切。
先後:打太刀側は大きく打ちにいき、仕太刀側は小さく動きをまとめて斬り落とす。打太刀の動きと同調しない・気を急かさない様に動く。結果的に負けることも大切な経験になる。
小太刀:波立での当拍子での動きは、受ける動きで表現する。これが出来ずにただ当てて動くと事故に繋がることを知る。打太刀の速さ・重さ・勢いに覆われると直ぐに出来なくなるので地道に丁寧に練習して練度を上げる。
越拍子:これは打たせる意図を持って練習することがまず一歩。躱すのではなく外すことが大切です