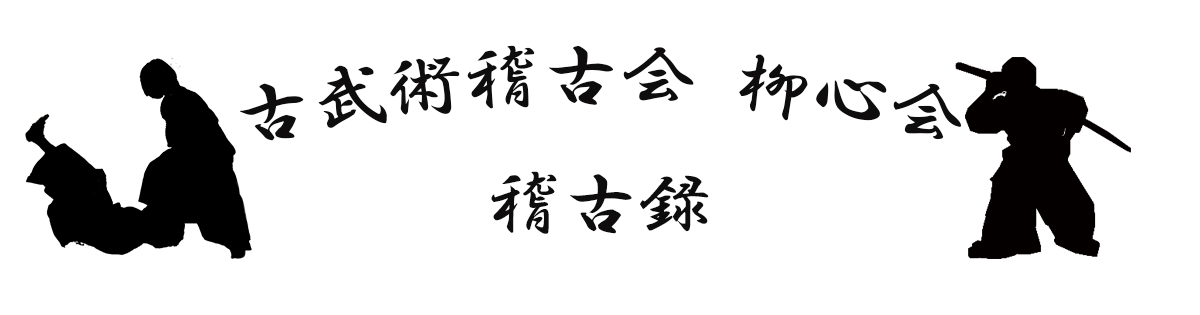古武術稽古会柳心会2025年08月16日稽古録
小太刀:構え・歩み・素振り・袈裟打ち・袈裟受け・入り・誘い
剣術:小太刀 打ち・受け・中心立(順・逆)・受け流し・
型稽古:波立・横雲・下段詰
居合:一文字抜・向・半身・坐居合:一・五・八・九本目
体術:下藤(背中伸ばし)

小太刀:この日は杖の自主稽古から小太刀の基礎稽古に変更して自主稽古開始。構えの作り方から歩み・袈裟打ち・受け、誘い(横雲)・入りなどの基礎から解説・練習を進めていく。
構え:太刀での作りを小太刀仕様にしながら解説していく。基礎の半身構えから、後手となる左手の扱いなど細かく伝える。特に左手の扱いに関しては徹底して欲しいが本人次第なので、各位の意識次第で上達への道筋が決まるかと思う。
歩み:先の構えから、目付・軸の維持などポイントを伝えて歩んで貰う。始めは鏡を使っても良いが、慣れてきたら内観で見極めながら練習して貰えればと思う。癖になると取り除くのが難しくなる。病になる可能性もあるので内観を育てる事。
袈裟打ち:上段に構えてからの袈裟打ち込み。慣れない動きで戸惑いが見えたが、日頃の練習から工夫して打てるようにして貰いたい。
入り:受けるのではなく縦に真直ぐ入り結果的に受ける。太刀が左横に来るので、怖さが先立つが気にせずに入る事が重要。間の入りに繋がる練習でもある。
誘い:横雲で使う誘いの部分を練習する。太刀を下して、構えを平行にとり打たせる姿を作り誘う。敢えて作る心持ちが肝要になる。まずは慌てずに丁寧に分解しながら練習して貰えればと思う。

剣術:身体の側面・前後を伸ばして、引き続き小太刀稽古に入っていく。軽く打ち・受けをしてから部分稽古で中心立・受け流しを練習する。
中心立:まずは基本の順での受けから中心立を練習する。打太刀は仕太刀側の動きを良く受けて固めずに緩んで受けられるように工夫して貰いたい。逆での受けから立てられた際の受けは先のより身体の緩みと流れを受ける事が重要になる。見本でみせた動きを見てから受け方を掴んで貰えればと思う。
受け流し:まずは体の入替を基本とした形から練習開始。前に出ずにその場で体を入れ替えて結果的に受け流す。結果を先取りすると上手くいかない。打太刀の太刀筋に対して余計な事をしないことが鉄則。その後は、姿勢による高低の変化で受け流す形も練習。
型稽古:波立・横雲・小手詰
波立:基本の動きから練習開始。当拍子・外しなど順次練習していく。当拍子・外しの時に仮想の受けが曖昧になり易い様子をうける。重く速い打込みでは受けが崩れるので、受けの形をしっかりと作ることが大切。当拍子のコツは、切先を付ける形を作ること。
横雲:先の練習を踏まえて型の練習を進めていく。これで型の手順と形が定まった感じ。あとは個々の動きを丁寧に練習するのみ。最後の体捌きは、前足→後足の順で半身の形を作る。(結果的に打太刀から身を隠す形にする)
小手詰:下段からの突きを押さえる練習から入り、型の練習へ。極意は膝の緩みで小太刀を扱って押さえる(腕や手で下げない事が大切)小手詰の動きは、肘・胸の緩みで小太刀を切先から扱う事が肝要。Zさん、功夫の力を存分に表現して柔らかい太刀捌きをみせてくれた。力を入れない事・中心の捉えで動く、緩みが先導してくれていた。

居合:一文字抜の「鞘引落」この部分を徹底するように練習する。袴を履いていても、仙骨辺りに運ぶ意識が必要。型稽古は、表・裏に分かれての練習。表は、一本目・五本目。裏は、八本目・九本目を練習する。
坐居合表:付からの沈みと誘いの際に、股関節と肘・胸の同時活用で誘いを作り次の動作に繋げていく。受け流しの際に、腕を立てる事を徹底してもらう。太刀の見え方には拘らない様にする。
坐居合裏:八本目を仮想のラインを意識して貰って練習する。切先返と中取の関係・左手の緩みと体の入替などを練習する。九本目は八本目の動きを踏まえての動き・形であることを示唆して抜いて貰う。八本目とは形式が違うことをまずは知る事が大切。