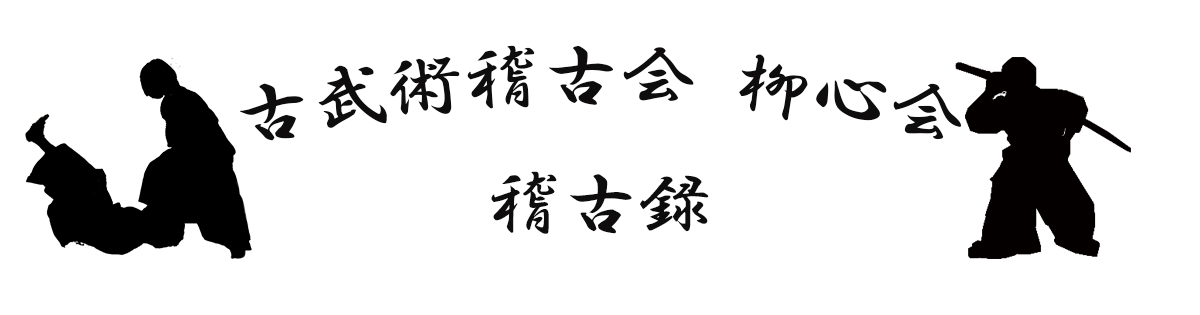古武術稽古会柳心会2025年09月13日稽古録
杖:膝の緩み・構え・一人杖・袈裟打ち・足払・縦回転(組杖二本目より)
型:組杖五本目・六本目
体術:手首の緩み・腕・胸の緩み(舞)・膝の緩み・詰崩・小手返(後受身)・仙骨崩
居合:一文字抜・腹抜突・縦抜・半身
型:月影・坐居合一本目・七本目・八本目・十本目
剣術(二刀):基礎・打ち受け・向満字(一足一刀)
型:向満字・中段・鷹之羽(一・二)

昼後にはブルーインパルスの滑空も観れるらしいが……(生憎の天気で中止になった、残念)稽古は小太刀から二刀の稽古へ。小太刀の学びをいかしながら、前へ進めればと思う。
杖:膝の緩みから構えへ。一人杖では、動きを大きく正確に打つことを心掛けながら練習を進める。動きに慣れてきたら、細かい部分を見直すためにも大きく動いて違和感を探るのが一つのやり方。
袈裟打ち・足払:旧一人杖で扱う技法を抜きだして練習する。速く動くと動きが小さくなりがちになるので、大きく正確におこなう。相対で相手をおいて、どの部位を狙うのか誘いの意味(初級)も感じながら。
型:組杖六本目・五本目
六本目:巻落からの動きにフォーカスして見ていく。打方は巻き落とされたときに虚脱して身体から腕を切らないことが大切。落される流れを受け入れて袈裟打ちに繋げていく。これは柔術の返しと同じ構造なので、難しくともトライして貰いたい。仕方は、弾落しからの極めの位置を関係性から掴んで貰いたいと思う。
五本目:仕方は打たせる、打方は打つ、この関係性とぎりぎりの間が学びとなります。中途半端な動きは曖昧な結果になります。適切な間・拍子の学びを優先して練習を摺る様にして貰いたい。

体術:手首の緩みから、腕・肘・肩、中心へ繋げて足を自由に動かして舞的な感じに身体を柔らかく静かに動かしていく。その流れで、膝の緩みへ。
詰崩:掌を合わせて、中心→軸の捉え→肩抜と繋げて受けを崩していく。この様な練習は、意味と意義を理解していないと時間の無駄になるので、何となく受けない様にする。受ける時に膝の遣い方を簡単に解説する。
小手返:受けに後受身を取らせる様に掛けていく。先の詰め崩しを受け手の流れが伝わっていなかったので反省。腕・手首から中心・軸への働きで崩しを掛ける。
仙骨落:Zさんへの崩しでは、軸を使っての崩しを試してみる。功夫による粘りのある下肢を崩す練習は良い学びになり助かります。

居合:一文字抜きから居合刀(模造刀)を使って各種素振りと移動する素振りを練習していく。移動しての素振りは各位に任せすぎていたので、今後は集団での練習も取り入れて工夫していきた。
縦抜:目線を下げずに切先にフォーカスして、速さよりも一致を大切にしながら練習をしていく。左足を退く時に身体が移動してしまい後退する人がいるが、軸の位置は動かさない想定で抜いていく。斬りと沈みなどの一致も大切にしながら練習する。
半身:軸の浮き上がりにフォーカスして、鞘引きの音を消していく。抜きと浮き上がりの一致が大きな課題となるので、小さいことから修正を各位それぞれ進める。
型稽古:坐居合一・七・八・十本目
課題を置きそれぞれがそれを意識して抜いていく。遣るべきことは堪えず変わらないが、練習・稽古を進める中で脇に置きがちになる。前提を課題として置くことで、改めて自分の抜きを見直していく。
八本目:この日の練習では、本来の体捌きでの抜きを練習していく。抜きと身体の拍子が合わずちぐはぐになるだろうが、遣るべき動きを忘れずに抜いて貰う。体捌きと切先が一致して、浮かして体を入れ替えていく。
十本目:刀の寄せ・差出・抜き出し・切り付け・二の太刀など遣るべきことが多いが、基礎の学びをいかして抜いて貰う。

剣術(二刀):二刀の基礎から練習を進めてみる。交点の扱い・感覚が身についてこないと二刀の上達は難しい。(間で動くとその辺りは曖昧かするが)受けの基礎的な形と体捌きを単体・相対で練習していく。受けにいく形は、木刀へのダメージと腕への圧が強くなるので初心者限定なので各自考えて練習をお願いします。退きは(間の感覚が無いと危険になり易い)あまりやらない様に、剣において間の伴わない退きは危険が絶えず伴います。
向満字:一足一刀の間合いでまずは練習していく。その際に間合いを体感してもらう。怖い感覚は非常に大切なので、その感覚を受け入れて動けるように一歩前に出る。十字受けからの小太刀の処理が大切。
中段:中段構えからの基本として練習してみる。気構え・位攻など少し解説しながら練習をする。手順からの練習ではあったが初心的な形にはなったので各位の地力を感じ安心した。
鷹之羽:一・二を練習。中段からの流れだったので形が取れれば良い感じで進める。二の受け流しは、各位捻ってしまい受け流しの理解と練習量が足りていな事が浮き彫りになり、今後の稽古に繋がる。受け流しをする時は、下肢を有効に使えるように工夫が必要です。