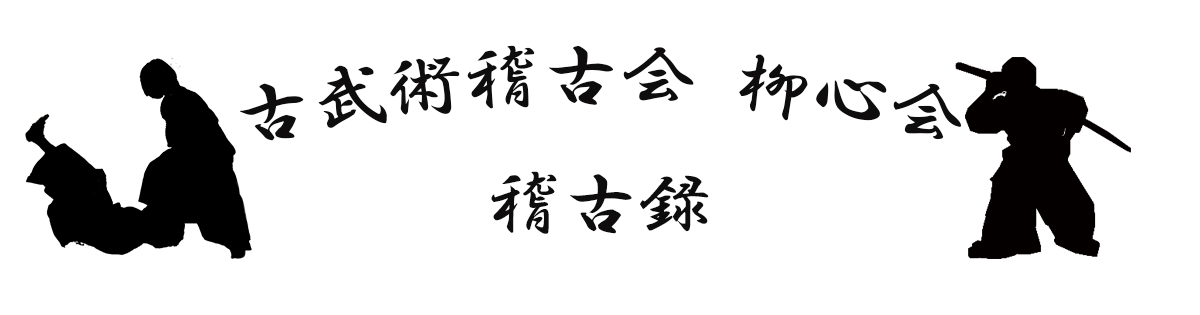古武術稽古会柳心会2025年09月20日稽古録
体術(自主稽古):手解・坐技呼吸法(基礎)・柾目返(基本1)・合気上
稽古場が畳だったので、体術の基本として肘の緩みにフォーカスして稽古を進めてみる。当会で学ぶ技術の根幹でもあるので、その一端が伝われば何より。
体術:軸作り・呼吸法・金剛指・足入替・膝の緩み・中心押・前受身・前廻り受身・小手返・腕返・背落・仙骨崩
剣術:構え・基本素振り・袈裟打ち・切返・切落詰
二刀:基礎・守り(素振り・打込み受け)・向満字・小太刀立・刀合切

稽古場の関係もあり自主稽古は、杖ではなく体術基礎として稽古を開始。課題は肘の緩みの遣い方。人が何気なく意図なく自然な緩みとして使っているものを改めて意図して使うための稽古。自然であるからこそ違和感なく発露する。
坐技呼吸法:両手首を押さえられたところから肘を緩めて、受け手の肩を詰め上げ、水平に移動させて落下を使って崩す。単純だからこそ動きの質を問いながら積み上げて自分を育てて貰いたい。
この様な稽古には、受け側の理解が練度に響いてくる。体術・柔の九割は受けが適切であれば防げるモノなので、受け過ぎる・防ぎ過ぎる事は百害としかならない。逆に掛けまいとする行為はこの様な稽古においては、何の意味も無い行為となり時間の無駄となる。互いの大切な時間を有効に使って貰いたい。

体術:背中のラインから腰→下肢へ流れをつくり崩す事がこの日の課題だったかと思う。その為の様々な技の練習と動きの解説だった。
中心押:軸を立てた受けの中心を横から真直ぐに押して、受け手は膝を緩めて働きを感じて受けていく。間を読んで・感じて先に動かないことが大切です。動きの見本から意図を感じる意識が大切です。
小手返:この日は、肩の抜きから軸へ働きかけて、螺旋の動きで崩していく。その際に横方向に広げずに掛ける事が大切になる。脇を広げずに緩めて使う。小手返自体は様々な掛け方があるので、学びになる技だと考えています。
腕返:肩の落としと受けのバランスを捉え、完全に崩しがどの位置なら掛かるのかを見ていくことが大切かと思う。掛け途中に余計な働きを作るとそこから返しが起きるので、流れを大切にする。
背落:下肢の崩れる関係性と真下とは何かを考えると出来るようになるかと思う。受けては体幹を固め過ぎない様に気を付ける。

剣術:構えから基本素振りへ。基本素振りで肘の緩み具合を見ていく。切先を意識しながら肘を緩めて縦に振り上げていく。ほど良いところまで上げたら、切先から必ず縦に切り下ろしていく。この時に前をしっかりと意識して切り下ろす様にしていく。
切返:各位の打ちを受けながら、一言指導していく。速さよりも道具と身体の一致を大切にしながら、両腕をしっかりと伸ばして打込んで貰いたい。慣れてきた人は、半身の入替をより意識してスムーズに出来るように工夫していく様にしていく。
切落詰:①切落②位詰③小手詰この三つの動き・働きを最短・単純な動きで学んでもらう。特に位詰めは初めての人も多かったので、解説を交えながら練習していく。小手詰は刃の方向を変えて、小手を適切に押さえられる場所に置く様にしていく。
二刀:向満字・小太刀立・刀合切
型稽古に入る前に、十字受けの形と交点を作る基礎的な道具の動かし方を練習していく。まずは一足一刀の間合いで型の動きに慣れて貰う。
向満字:刀を小太刀で押さえながら、大太刀を抜く動きが曖昧な会員が多い。軸を保ちながら下肢を退く動きを学んで貰えればと思う。そこから刀を立てながら切り付ける。
小太刀立:これはい入り身が肝要となる。特に膝を緩めて受け手の側面を滑る様に移動することが足遣いの学びになります。
刀合切:刀の運用が見て取れない様子だったので、後半は詳細を解説する。感覚としては、絶えず守りながら次の動きに入る様にしていく。刀合切は個人的には中心詰の形が好きなので、そのうち集中して練習・稽古できればと思っている。