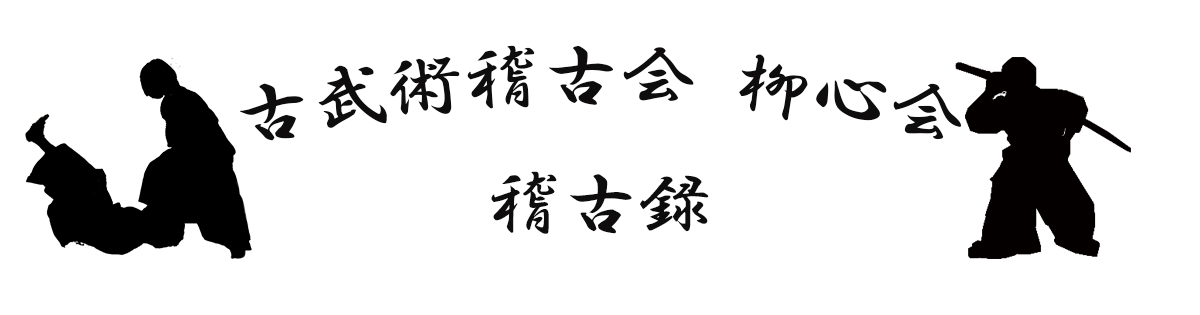古武術稽古柳心会2025年10月18日稽古録
杖:構え・左右入替・袈裟打ち・切先返・打落・一人杖(新・旧)
型稽古:組杖4本目・巻落
体術:膝の緩・構え・構え入替・側面入(崩し)
居合:一文字抜・腹抜・表一・二・各自課題型
剣術:正眼構え・基本素振り・廻剣・切返・片手袈裟打ち(左右)・片手中心立
型稽古:二刀 向満字・小太刀立・大太刀立・正眼破
二刀剣術も今月で納め。毎年この時期に小太刀・二刀と稽古してきたが来年あたりは、少し修正していこうと思案中。基礎の技術と習得すべき型にもう少しフォーカスしていこうかと思っている。なんにせよ来週で今期の稽古は終わりなので、少しでも前に進める様にと思う。

杖(自主稽古):構えと入替から稽古開始。構えの取り方から全員で見直していく。膝を緩めての基礎の突きを暫しおこなってから袈裟打ちへ。
切先返:その場での打込みで進めていく。道具を立てる瞬間を必ずつくり、体の入替と一致してまずは形が取れる様にしていく。速さで誤魔化さずに、立てる技術を少しでも深めて貰いたいと思う。
打落:打込みながら、道具の長さを隠すやり方などを解説する。素振り壁に当たりそうになり一瞬ひんやりする。慣れない動きは気を付けていかないと反省!!ことらも威力は求めずに、一致を大切にしていく。
一人杖:旧版での松風からの打ち払い→縦回転にフォーカスして解説する。指導を受けた頃この動きが見えず、分からず難儀したのが懐かしい。今は敢えて一歩踏み込む形を取っているので大分見やすくなったかと思う。基本はその場での体捌きなので分かりづらいのは、当たり前だが……。
型稽古:組杖四本目
この型ではまずは、中心を捉えることが第一。肩の抜きにフォーカスすると忽ち崩れて出来なくなる。心理的な働きが動きに影響するのが良く分かる。打方にも適度な感度が求められるから、内容的には上位の型かと遣りながら再認識する。
巻落:前半部分にフォーカスして稽古を進める。途中、巻落の働きが弱い場合は返して崩しを掛けていく練習も少してみる。拍子と間を見る良い練習になった。

体術:構えの取り方、体の入替の注意点を見直しながら進めていく。その流れで側面入りを久しぶりに稽古してみる。受け手の側面に丁寧に無駄なく入ることを念頭に稽古を進める。慣れてきたところで、受けは取りの間を捉える形で稽古を進めていく。この稽古で大切なことは、入りを邪魔する事ではなく、動きの出だし(余計な動き)を相手に知らせる事。また、間を感じるのに適した握りを知る事も。
居合:腹抜の際に左膝の緩みを活用して、抜き出す練習をおこなう。自分で流れをつくり、留まらずに丁寧に抜く。この動きは、型稽古で非常に役立つので時間がある時に少し練習して貰えればと思う。
型稽古:表一・二・各自課題型
表:横払いでの注意点を解説していく。切先が始めに向かう方向と位置、胸の使い方、幅など。二の切に関しては、これまで稽古してきた型と変わらずにおこなう。
私も少し自分の稽古をする。軸の位置、浮き上がり(浮身)、切りとの一致など。基礎・基本の延長に有る事をどの様に深めていくか。居合は基本的に自主稽古となる。その視点をもって相手と向き合って稽古が出来ればと思う。
剣術:切返から片手袈裟打ち・片手中心立などの二刀剣術にとって大切な動きを稽古していく。小太刀の身遣いがあっての二刀だが、視点を変えて小太刀稽古で何を学ぶのか知って貰えれば何よりかと思う。

型稽古:向満字・小太刀・大太刀立・正眼破
受け:向満字でまず身に着ける十字受け。この位置を何処に無理なく置くかが、最初の課題となる。物理的に強靭な位置ではなく、打太刀に対して、適切で身を護り、取っているところが求められる。様々な打ちを経験して、自分で掴むことが力になる。
立てる:片手で適切にどの様に詰めるか、これが小太刀・大太刀立の難問となる。打太刀の感性(柔らかさ)も適切に求められる。見本で動いたら、型と違う形になってしまったのは、私としては反省点!!
正眼破:動きを分解しながら、手順で稽古をまずは進めていく。構えを打太刀に対して、隙なく取り、小太刀構えそのままとなる。三角の正眼に対して如何に崩しを掛けていくかが大きな命題となる。太刀の切り付けと中心への働きかけ(捉え)など、各位の工夫が必要な感じではあるが、動きの要点は理解して貰えたので何より。