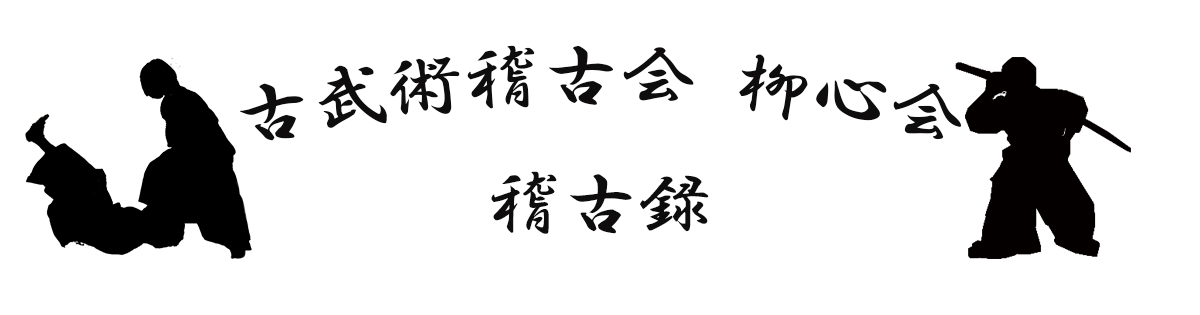古武術稽古会柳心会2025年10月25日稽古録
自主稽古:小太刀構え・歩法・寄り・詰め・受け流し・二刀素振り・体操・正眼破(半身入替)
剣術:廻剣・
小太刀:波立(基本・当拍子)・受流・浦之波・両手切(入門)・詰切
二刀:向満字(車之構え)・双捲・柳雪刀・正眼破
当期の小太刀・二刀剣術は今日でいったん締めとなるのでしっかりと稽古が出来ればと思いながら稽古場へ。反省点としては、稽古内容をしっかりと決めて臨めば良かったと反省。この辺りは来年の大きな課題なので良い方向に修正していきたい。会員それぞれ良く稽古してくれていた成果が出ていたので良かった。打太刀の難しさも感じてくれていたので、来年に繋がる良い傾向でもある。

自主稽古:先ずは小太刀の構えから入る。構えがとりあえず取れる様になれば、小太刀稽古している意味もある。半身をしっかり取り少し前掛かりになり、刀(剣)に体を入れていく。特に道具を持たない手の処理をしっかりとすることが大切。長く稽古していても取れない人もいる。意図をしっかりと図ることが稽古ともいえる。
各種基本:構えをとってから、歩法・寄り・詰めと相対で稽古していく。小太刀という圧倒的不利な道具を持ちながら、心身を遣い制する一端を其々から確認してもらう。特に詰める技術は切落を踏まえての要素となる。これが出来てこないとおさえる技術に繋がらないので各位の工夫に期待する。
受け流し:受けから半身の入替で練習していく。小太刀での受けから交点をずらさず身体と中心への捉えを丁寧に使っていく。身体が下がると打太刀に詰められる可能性が出てくるので忘れないで貰えればと思う。
正眼破:大太刀と小太刀をそれぞれ持って、型の手順に沿って半身の入替で打っていく。片手での袈裟打ち・大太刀での詰めなどなかなか学びがいのある動きとなる。特に打っていて身体の丁寧な半身遣いの訓練にこれはなかなか良いことに気が付く。今後の稽古でも思い出したらやっていきたい。
剣術は廻剣を準備運動として大きく三拍子で打っていく。背中・胸・掌の扱い・末端の意識と動きを分解・繋げる事で基礎を構築するのに良い稽古になる。時間を掛けて意図さえしっかりしていればこれだけでの良いかもしれない。

小太刀:自主稽古の流れを踏まえてさっそく型稽古に入っていく。当会の基本である波立から始める。基礎は会員それぞれの段階で良く習得しているので当拍子に入っていく。
当拍子:今期から指導を始めた技術だが、各位一定の理解はした感じは受けたので良かった。ただ当たる時に下げたり、受け流す形になり易いことが分かったので来期はそれを踏まえて稽古が出来ればとおもう。
浦之波:この型も間合い・拍子・間と様々な事柄を学べる良い型。小太刀上段の質問が有り解説し忘れていたことを反省!!。経過動作を学ぶにも良い動きなので、立ち止まり易い人には学びが深いかと思う。
切詰:型ではなく、技の練習を最後に少し行う。縦に螺旋に詰める技術、これも小太刀ならではの雰囲気があるので面白い。動きの一端でも見てくれれば良いかと思う。
二刀:正眼破から稽古を開始。付からどの様に刀を下げる(誘う)のか伝わっていない様子。この動きは通常の稽古の中で当たり前に出てくるので、今後の課題として楽しんで貰えればと思う。片手袈裟打ちの雰囲気は伝わった手ごたえがあったので良い感じだ。
双捲:車之構えからの寄り方は、二刀ですると動きの理解度が出るので出るので中々面白い。打たせて捲る感じと打ち・払いの違いを捉えられれば一歩前進かと思う。なかなか見ない動きなので稽古していて面白い。
柳雪刀:苦手な動きをいかに自分のモノにしていくかが学べる型。誘いと縦に動きをぜひ自分のモノになる様に、胸を柔らかく背中もしっかり使って下さい。
向満字:最後は向満字(車之構)で締める。この日は無形ではない形で稽古して貰う。より誘いが生きる形なので、気持ちを前に出して、柔らかく十字受けを取り切り付ける。気を楽に楽しい雰囲気があったので良い感じだった。

今期の小太刀・二刀稽古も無事に納める事ができました。少しでも身になる稽古で有ったのなら何よりです。難しい事・動かない事・見えない事、そんな儘と感じる事柄を楽しんで貰えれば。