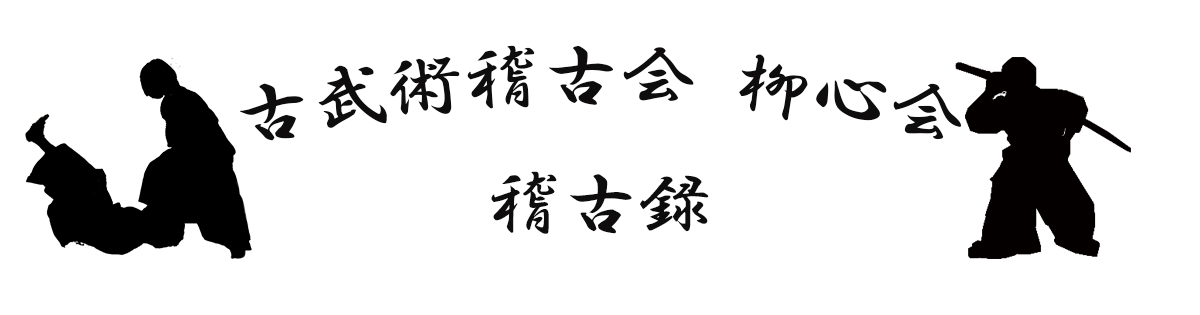古武術稽古会柳心会2025年11月01日稽古録
自主稽古:前廻受身(工夫)・杖:袈裟打(その場・前後進退)・組杖:二本目
体術:金剛指・構え(左右・入替)
居合:構え(基本六法)・素振り基本・上段切付・一文字抜・腹抜・腹抜突
表:一~三本目・坐居合一本目
剣術:廻剣・袈裟打ち(基礎)・切返(各種工夫)・打ち・受け・中心立
型:基本組太刀一本目

杖稽古に入る時にAさんの練習でしていた前廻受が気になり、急遽要点解説をおこなう。
廻受身:①腰を縦に廻す(臍が正面で転がる)②極力蹴り足を作らない様にする③指先を指針として使う⑤まずは仰向けになり、指先の方向を正す。
これらの動きを解説しながら短い時間ではあるが練習してもらう。Aさん、良いきっかけになったのか動きが良くなる。基礎の動きを正しく表現できれば各位の段階で表現できることが見えて何より。姿勢を低くする事と頭を下に運ぶことの違いも注意点として伝える。
杖:袈裟打で両腕を伸ばす方法と左肘の遣い方との関係性を解説する。肘が過伸展状態にならない様にし尚且つ緩めておくことが非常に大切になる。この腕の使い方を心掛けるかどうかで、間合いを体得するためのきっかけを掴むための道標になる。この使い方は切にも直結するのでよくよく考えて工夫して貰いたい。
組杖:二本目
袈裟打の延長で二本目の稽古に入り、仕方・打方の動きをとおして理解を深めて貰う。各位素直なので、稽古した動きを良く表現できていた。杖先の方向と縦回転時の先をいかに使うかが今後の課題かと思う。

体術:金剛指から螺旋運動を使って緩めていく。末端の使い方と連動・繋がりを練って貰う。この動きは各位それぞれ身体全体へ延長できれば、身体を練る動きに転用・工夫できる。突きの動きを使って、内面を踵から繋げていけば打撃力の向上も図れるかもしれない。知覚を広げ繋げて貰えればと思う。
基礎的な構えを使っての打突方法についても少し話をする。守・攻のバランスを少し調整できれば護身的な使い方の一端を表現できるようになる。本筋ではないが考え方の一つとして知っていて貰えればと思う。
居合:模造刀を使って、各種基本の構え・素振りを稽古していく。扱う道具が変わればその性質に導かれて、いつもと違う感覚になるので面白い。素振りにおいては、立てる事・切先の意識・肘の緩みになどの基礎にフォーカスして稽古していく。
腹抜:三角の付き方とその意味を解説する。切れるものを扱うという事は一寸の距離感で、その動きの正否が変わってくる。相手がいる・いないに関わらず動きを丁寧に練っていきたい。鞘の遣い方と足との一致もこの日は丁寧に稽古していく。
表:型の手順をまだまだ修正している感じで、迷惑をかけて申し訳ない。三本目の一之太刀についてまだ決めかねている。左への動きがここまで難しいかと改めて、師匠の言葉を思いだす。基本的な位置づけではあるので、段階をどの様にしていくかが問題……。
坐居合一本目:付からの誘いと体捌き、廻刀について会員を見ながら思案する。肘の緩みと立てる動き、廻刀。二之太刀の形式に少し拘り過ぎたかもしれないと反省。

剣術:廻剣で身体をほぐしてから、剣術稽古へ入っていく。まずは袈裟打の精度向上から。
袈裟打(相対):腕・肘の遣い方、切先の意識、身体と道具の一致を見直しながら打込んでいく。この稽古でそれぞれの袈裟打ちを修正する力を身に付けて貰えればと思う。出来る様になるのは自分だという事を忘れずにいてほしい。
切返:現状の動きを見ながらポイントを各位に伝えていく。腕を伸ばし打込んだ姿勢で、体捌きを中心にして打っていくようにする。刀を極力引かずに丁寧に打ち中心を捉えていく。最後の工夫として片手打ちと膝の沈みが一致する様に修練してもらう。そして通常に戻り、動きと威力の変化を見ていく。それぞれ上達して、打込みが重くなり、中心への捉えが変化して、何回か安全の為に間合いを外してしまった。
中心立:身長差による受け方・立てる際の方向などについて解説して理解を深めて貰う。この高低の差を理解できていない人は多い。背丈・腕・足の根本的な差は、技術の難しさ、方向と直結している。だからこそ差を理解しそれぞれの形に要点を修正していく必要がある。それが結果として個性ある動き(その人本来の正しいやり方)へとなっていくと考える。
型:基本組太刀一本目
手順のおさらいから、打太刀・仕太刀に分かれて型稽古に入っていく。今の段階では、先ではなく手順として行っているので、難しく考えずに手順と形を俯瞰して覚えて貰いたい。会員から質問があり、体捌き・緩みの差による動きに違いについて示唆する。速さは結果なので、幻を求めない様にして貰いたい。動きの基礎を見直して、大切な要素の向上を目指して貰いたい。