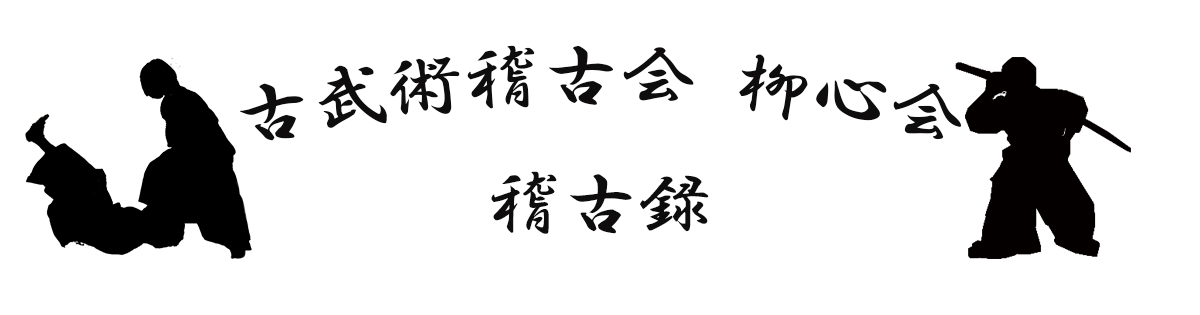古武術稽古会柳心会2025年11月08日稽古録
地元の桜並木もゆっくりと彩を深くしはじめた今日この頃。この日の稽古内容を考えながらゆっくりと稽古場へ向かう。基本組太刀の初伝遣いを伝え動きと形をできる様とも思いながら。
杖(自主稽古):構え・三方突・弾き(相対)・組杖:三本目
体術:金剛指・膝の緩み・構え・体入替・一致突き・突き躱し(入身崩)
居合:一文字抜・腹抜突・縦抜(工夫)・型:表一~五本目・各自課題型
剣術:廻剣・打ち・受け・中心立・受流・木葉流・型:基本組太刀一~三本目

杖:上の会員が多かったので、構えを取ってから三方突きへ。
三方突:左右への付への意図を明確にしながら、動きを大きくし稽古していく。慣れてくるに従い動きを内面化していくのが定石だが、其れによる動きの角が現れやすくなる。今のところ動きはさほど小さくならない様にしている。本質的にはその辺りは個人が工夫すべき部分とも考えている。
弾き:単式での稽古は初めてだったかと思う。先ずは受けの位置を会員それぞれがしてから稽古して貰う。なぜ始めに受ける位置を掴んでもらったかの理由は稽古中に伝えたとおりなので、今後の稽古でもいかして貰いたい。打ち払うのではなく「弾く」遣い方を体捌きと共に工夫して下さい。
組杖:三本目(対剣)
打方は刀(木刀)で稽古してみた。この型の稽古をとおして長物の優位性と間合いの変化とその対応への心構えなどを伝える。上位者が多い時の特典的な稽古になったかと思う。打方することで、打込む難しさも感じて貰えたようで何より。その感覚を知る・持っているかで型への対応が変化します。
動きの要点としては、各位末端の使い方は良かった。誘いの方便と間合への入り方は個性が出てて面白い稽古になったかと思う。
体術:金剛指から膝の緩みへ。この日は膝の緩みへの誘導を少し小さく練習して貰った。
突き躱し:先週に引き続き構えの遣い方を稽古する。体の入替と構えで十分体術の稽古となる。一致突きを構えの入替で入身し、首部へ崩しを掛けていく。この時に上部の腕・手で払う動きをしないことがポイントの一つ。受け方が入ってくる流れをいかして最小の動きで、中心を取り崩す。一拍子でおこなわず先ずは二拍子を流動的に繋げて遣る様にする。この段階を踏まずに稽古すると殆どの人は曖昧な動きとなる。身体はイメージどおりには動かず遅いので均すことから。

居合:一文字抜と腹抜突きで先週の復習から縦抜(工夫)へ入っていく。
縦抜:抜き出し、鞘引、片手斬り、納めを工夫しながら稽古していく。まずは速さではなく切れ目のない大きな動きと一致を求めて貰う。特に左の体捌きと鞘引の一致を徹底して習得へ向けて稽古して貰いたい。最後の納めについて稽古もしていく。悪い意味で適当になりやすく、気付きづらいところでもあるので位を示す気持ちで稽古して貰えればと思うが……。
型:表一~五本目
懸案の三本目は切上(逆袈裟)で抜いて貰う。最初の段階としてはこの形で稽古していく流れになりそうだ。別伝として稽古する流れにしても良いかと考えたりもする。
四本目は敢えて構える形を作り修練する流れとしたがどうだろうか。状況・動き・先への布石など詰めていくかどうかだが。
五本目は手数が増える形になる。まずは各動作を丁寧に出来る様にしてください。型の手順と意味を理解して動くところから。速さの誘惑に負け形が崩れない様に注意が必要。
剣術:廻剣から初めて身体の固さをゆっくりとほぐしていく。稽古の流れを確認しながら打ち・受けから入っていく。
打ち:当会の打ちは流れを切らさない、受け手への働き掛けを消さない事を念頭に置いて一拍子・一致した動きで打込んで下さい。楽をするために停止した打ち込みをする人いる。当会ではそれは稽古の妨げになるので、丁寧さを忘れずに工夫して下さい。
受け:三角の形を作り前で受け、上下を護る。これらのポイントを守れる位置を、変化する打ち込みの中で見つけて下さい。簡単ではない事なので焦らず、失敗することで見つけて貰えればと思います。

中心立:受けを踏まえて、左手一本で胸の緩みを遣いながら立てる動きを見直して貰う。やるべきことを正確にすることが大切です。成功に固執しない(我を内在化する)ことが剣術の技術稽古では大切になります。
受流:まずは右側の受け流しから稽古していく。右腕を立てながら胸を緩めていく。この時に分離が大切になります。稽古時に話したとおりそれぞれの動きに引きずられない事を念頭に失敗してください。
型稽古:基本組太刀一~三本目
型の手順をおさらいしながら、各位の動きを観ながら修正点、ポイントを伝えていく。段階的な稽古と習得を考えているので、云うべき内容は其々で異なります。自分が何を習得するのか読み取って貰えると次に繋がるかと思います。
二本目:体捌きと受ける位置の把握が仕太刀の学ぶべき最初のポイントとなります。これらの動きは高伝以降の技術に直結しているので良く練習して貰いたい。捌ける人は間と拍子を捉える様にしてください。
三本目:動きは一本目の終わりの部分と同じですが、稽古時に伝えた要点を精度を深めてできる様に。