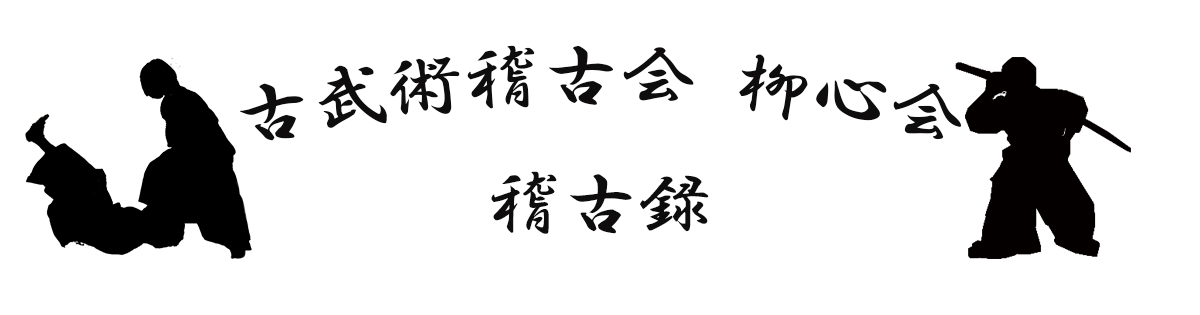古武術稽古会柳心会2025年11月15日稽古録
居合(自主稽古):一文字抜・表一~五本目
体術:軸作り・呼吸法・グランディング・膝の緩み・受け(肩抜)・構え(入替)・側面入り身・四方崩
剣術:構え・廻剣・袈裟打ち・切返・中心取り・基本組太刀・連刀

自主稽古:この日は杖術ではなく居合術から。一文字抜きから鞘運びについて暫し話をする。先週長年の疑問点が解消したのでそれを踏まえて、上帯での稽古も今後は少しやってみようかとも思う。
表型:横払の抜き方、どの辺りを基本として切るかなど動きの要点を解説していく。まずは水平に刃を扱うことが目標になる。そこから体との一致、その先となる。右腕の処理と抜き放つ方向と点のコントロールが難しく見えるが、それぞれ丁寧に抜いてくれていたので有難い。
三本目:しばらくは切上の形を基本として稽古を進める予定。左への抜き放ちは中々に難しく身体の処理に苦労しそうだが、そこに練る意味が出てくる。身体を練るのも居合の醍醐味かと思う。
五本目:動きの手順から型の内容と身遣いを一致させながら型を抜いていく。抜きから中取、刀押さえを分解しながら練習していく。分解された動きを流れの中で一つに纏めていくために今は丁寧に稽古して貰えればと思う。

体術:軸作りから呼吸法、グランディングへ。これらの技法は意義深ので、その都度短い時間ではあるが集中してやって貰いたい。居合稽古からの流れであったので、心身を上手く納める感じが出来たので良い感じになった。
膝の緩み:股関節だけではなく、足首・膝も合わせて緩んで崩れていく流れを作れる様にしていく。下肢全般を緩める感覚を掴むためなので稽古中に工夫して使って貰いたい。
側面入身:膝の緩み・股関節の緩みで崩すやり方を掴んで貰う。斬る動きと同じ遣い方なので前を意識して下肢を緩める様にする。指先・肘の使い方も大切なので忘れずに深めて貰いたい。
四方崩:始めに手首の持ち方と手首・肘・肩→中心への抜きを螺旋の動きを使って練習していく。この際に自分が動くのではなく、受け手を動かしていくやり方を掴んで貰えればと思う。相手を捉えることがその第一歩になる。崩しの流れから、転換と受け手の腕を立てる形を練習しながら四方崩の形を学んで貰う。

剣術:構えから廻剣へ。大きく柔らかく身体を遣いながら振っていく。切先を意識しながら胸の緩み・立てる事などをみていく。呼吸を使うと胸の働きが捉えやすくなるので工夫次第で上達に繋がるかと思う。
切返:各自それぞれの段階で太刀が速く重くなってきた。次の段階へ向かう準備を進めていければと思う。押しつけではない重さ、腕力に頼らない速さなど徐々に掴んで貰いたい。
型導入:基本組太刀三本目の形を借りて、中心取りを稽古していく。前提として中心への捉え方と前に入る動きが必要となる。手数が少ない型だからこそ学べる動き。
型稽古:基本組太刀
二本目:各位の動きが良かったので、次の段階の動きを最後に稽古する。体捌きと太刀打ちの一致が必要になる。何となくこなしていたので、上達の度合いが見て取れて良かった。
四本目:手順は各位問題なく稽古を進めていく。最後の太刀捌きで腰が引ける、捌きが浅い等の動きもみえたが今の段階としては悪くない。慌てずに打太刀の間を捉える様にして貰いたい。
五本目:間を捉えた上で待つことが初伝遣いの眼目となる。打太刀の間を取った車の打ちを抑えて返し、太刀の動きを待って打ち落とす。特に打太刀の動きに囚われて待つことが出来ず反射で動きやすいので、型の手順をまずは念頭におくこと。待たなければ落ちないことを知って貰いたい。
六本目:稽古中に型の勝ち筋と崩し(砕き)の勝ち筋について知見が広がる。まずは型の勝ち筋をしっかりと理解し覚えて出来る様にする。初伝遣いでは速さに拘らないこと。速さと間の動きに速さは関係ない事を覚えて知ることが大切。