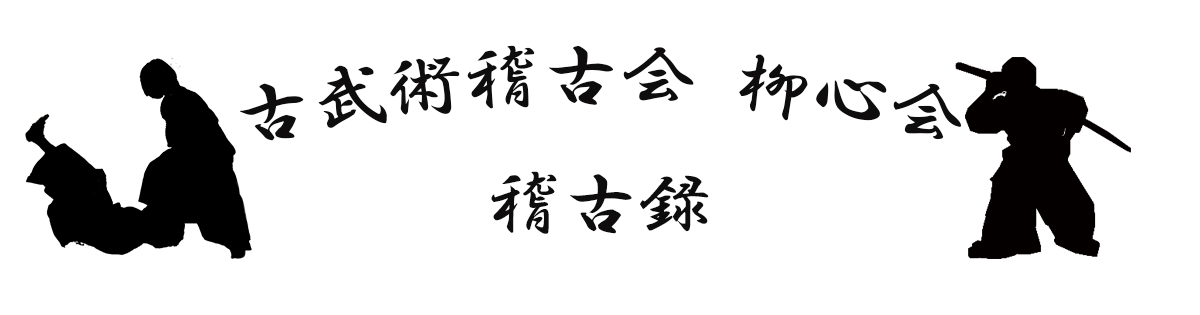古武術稽古会柳心会2025年07月05日稽古録
杖:膝の緩み・廻し杖・松風・巴・逆突き・三方突・一人杖(新・旧)
型:組杖4本目
柔:膝の緩み・身体の緩み(龍・鷹・虎)・前廻受身・構(入替)
型:側面入身崩・カスミ当・両手取・撞木小手返
居合:一文字抜・床返
型:鍔返・後影身・各自課題
剣術:構え・基本素振り・廻剣・下段突き・上段切付・切返・受流
型:三角切留(段階別稽古)
まもなく梅雨明けの夏空の下稽古場へ。身体もゆっくりと夏に順応してきたこのごろ。稽古場の窓を開けてゆっくりと掃除。この時間は自分の思考を落ちけて稽古の方向などをとめどなく考えていく。

杖:巴の基礎→基本形へ練習していく。日頃行っている動きは基礎(導入)なので稽古した形が基本(捌く動き)なのでよろしくお願いします。逆突きは必ず膝の緩み・体の入替と一致できる様に始めはしっかりと意図して練習していく事が必要。
一人杖:先週に引き続き旧バージョンも練習していく。この日の稽古場は高さが有るので、縦を意識して杖を扱っていく。振るって振るわずにコンパクトに扱っていく。
型:組杖四本目
まずは基礎となる中心押しの形で動きをみがいていく。中心を捉え・取らない動きでは、崩しが上手く掛からないのでよくよく稽古が必要。最後は受けの稽古も兼ねて肩抜の本式で稽古していく。この肩抜には受け手の癖を見極める必要があるので、掛けることに固執しないことが続けるコツ。打方は仕方がつくる流れを良く読み取って適切に動く様にする。

体術:十二形・十大形から動きを借りて、龍・鷹・虎の身法で上半身を緩めていく。背中・胸・肩甲骨と各動きであたためていく。特に虎形の打撃法は懐かしく、カッチフが自然に出てしまったのはご愛敬……。
前廻り受身:この日は久しぶりに基礎の形で腰まわりを縦に廻し結果的に前廻り受身(頭部を入れ込む)になる様に研鑽。ここから受身の工夫になるので基礎の確認を兼ねて身体に根をおろして貰いたい。
側面入身崩:上位者には交点の圧を変えずにより切込む形で練習してもらう。この形は側面でありながら向身の入り身になるので楽しんで貰えればと思う。他の会員も基本の動き(入り)の要点が身についてきた感じが出てきた。
型:撞木小手返
相手が固めた形の状態での掛け方を見せて動きのポイントを見取ってもらう。本来固めた相手に技を掛ける必要は無く、意味がないが柔らの動きが表に出やすいので見る稽古になるかと思う。
居合:柔の流れで床返から稽古開始。この日はAさんが来てくれていたので、良い見本を見れたかと思う。刀の寄せを曖昧に遣る人をよく見かけるが、大切な動きなので忘れずに丁寧に動いて貰いたい。
鍔返:肘の緩みを意識した稽古をおこなう。手首を使わぬこと、これは当会の動きの大切なポイントなので無自覚に使っている人が多いので気を付けて貰えればと思う。逆袈裟のラインを意識して抜いてください。
後影身:設定状況から解説。軸の傾斜と膝の緩み、刀の返しと難しい要素が多い。慌てずに一つずつ修正して積み重ねて稽古を。

剣術:付素振り左右時の膝の遣い方について少し解説。この緩みで袈裟のラインを作るので内観を育て、少しずつ自己修正できるように各位工夫をして下さい。
切返:各位の段階と進捗を捉えながら、それぞれに助言していく。上位の人は、引きを消す工夫と体の入れ替え。稽古時に伝えられたポイントを今後の稽古で、自分の動きに落とし込んで貰えればと思う。
受け流し:まずは定位置での相対稽古から始める。この稽古では動きの慣れと概念の理解が第一になる。そこから動きの精度に重きをおいて向上させていく。各稽古の本意を絶えず確認して、それぞれストレスを抱え込まない様にして下さい。これらの稽古では、実は仕太刀より打太刀のほうが数倍難しくなる。打太刀の基本は柔らかく斬り続けながら、中心を捉え続ける事。
型:三角切留
受け流しの動きが実際どの様に使われるのかが分かりやすいのでただ何となく熟さず、動きをそれぞれ良く考える癖を持って貰いたい。段階に合わせて強度を掛けていく。強度に対する各位の動きに個性と段階が見て取れて、学びになる。向き合いながら稽古を重ねていきたいもの。