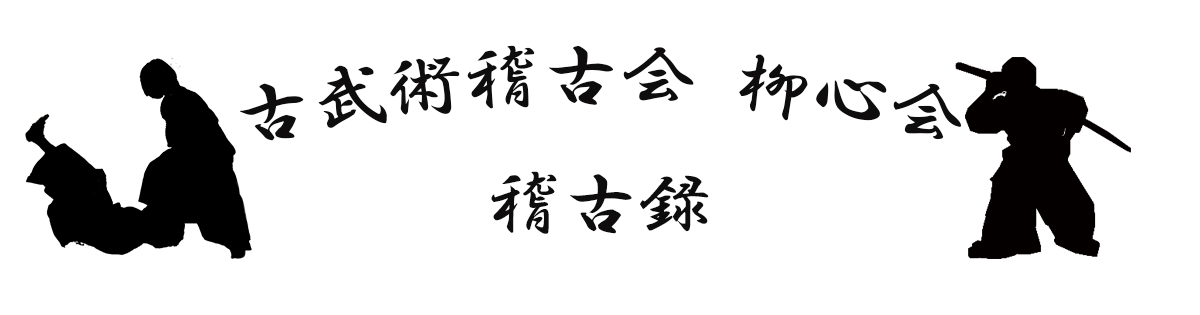古武術稽古会柳心会2024年12月14日稽古録

杖:身体を温めるために袈裟打ちの数稽古から。両端を意識しながら、腕・足をしっかりと使って全身で打ち込んでいく。その流れで一人杖へ。表・裏と数回繰り返すと身体も動ける感じへと。
巻落:受けの注意点を意識しながら、交互に練習。柔術に限らずどの様な稽古でも受け(打太刀・打方)しだいで結果は変わるので漫然と受けることはしない。流れを感じそれに従う。巻落のポイントは①中心を捉えはいっていく②それを踏まえて螺旋の働きを加えていく。
組杖:逆から順番に稽古を進めていく。頭の体操も兼ねて、柔らかく使っていく。
飯縄:巻落から打たせて捌く際の足遣いは、基本組太刀二本目と同じ。慌てずに捌くことがポイント。
大山:体捌きは、打ち捌きから身体が動く。此処の理解が追いつかないと上手くならないので、一動作ずつ動きを確認していく。
赤城:切先の返しと打ち込みはシンメトリー。これが誘いと間の一致。
愛宕:打たせること。これに尽きる。この日の稽古は工夫として、仕方は自由に動いて取る稽古も。頭を柔らかく、固定しない。

体術:龍・鷹の基本形を古武術式に工夫して、上半身の可動域を緩めていく。丁寧に行なったお陰か血行が良くなり肩も軽くなる。
受身:膝の緩みが受けにおいてはどの様に使われるかを稽古。受け入門といった形になったかと。後受身は小手返・前受身は肩抜落を使って動きの中で体感して貰う。技の流れを感じ、その方向の下肢を緩めて乗って受けを取る。取の動きと一致する。
手解肩返:この日は受けにおもきをおいて練習する。取は適切に掛け、受けは流れに乗っていく。これは漫然と受けを取り成り立たせることでは無いことを感じ取れればまずまず。

剣術:廻剣のポイントを意識しながら練習。車之打ちは体捌きから、段階を踏みながら縦の動きになる様に。
車之打:まずは体捌き、それに刀(木刀)を合わせる。相対で打つべき場所を意識しながら練習していく。
切落:相対で間を詰めて斬りかかる動きの中での切落。古典的な型稽古の趣になったが、各位の段階稽古になったかと思う。打ち掛かる側は、肩先を切り裂く様にしっかりと打ち込む。斬り落とす側は、構えをしっかり作り動きの間に合わせていく。半身か向身どちらも身構えが大切。
三角切留:先の動きを踏まえて初伝遣い・高伝遣い(入門)と先の動きも稽古する。初伝遣いと高伝の何が違うのか、段階を踏みながら。それぞれの理解の試金石になったかと。
基本組太刀
この日の稽古は結果的に六本目の修正とそれぞれが自分と向き合う稽古になったかと思う。この型は誠実に稽古すると非常に難しく、適当(正しい意味で)が求められる。まずは手順を正しく覚え、下手になる。その上で抜くために必要な技術を高めていく。打ち勝ち→抜き返されて→抜き返す→詰める。合気の状態になると打太刀には勝てないことを知る。後から考えると身体の遣い方と鍛錬方法を明示していなかったので、レベルが上がってしまった感が有ったのは反省